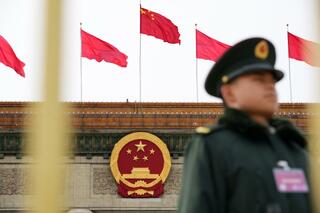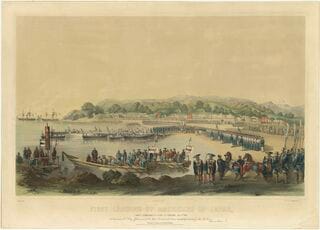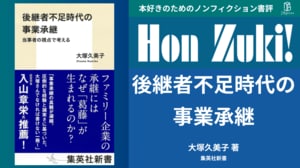眼窩(がんか)の空洞や大きく広げた口腔にも、蛆虫がぎっしりと詰まっていた。首筋の皮下には体長2ミリメートルほどの小さな蛆虫が、表皮を浮き上がらせながら動きまわっている。その様子は、水中を泳ぐオタマジャクシのようだった。
さらに、その合間を無数のアリが腐肉を運んで行進している。ボタンの開いたシャツの胸もとには、赤や黄色の毒々しい原色をまとった体長5センチメートルほどの虫も群がっている。虫に関する知識がない私は、原色の虫を見た瞬間、毒蛇のイメージと重なり思わず背筋が寒くなった。
のちに調べたところ、遺体の胸もとで発見した原色の虫は「シデムシ」の一種だったようだ。漢字で「埋葬虫」と書くシデムシは、動物の死骸などをエサにする死肉食の甲虫(こうちゅう)で、腐肉のほかに蛆虫も捕食するという。シデムシにとって蛆虫だらけの腐乱死体は、恰好のエサ場だったに違いない。
 シデムシ(Evanherk, CC BY-SA 3.0
シデムシ(Evanherk, CC BY-SA 3.0 この遺体のグロテスク度は、私が見てきた腐乱死体の中でも群を抜いていた。
遺体回収という大仕事
真夏の直射日光にさらされ続けた遺体は、手足の指が赤黒く干からび、一部がミイラ化していた。発見現場の撮影を終えると、次は遺体の回収となるがこれが厄介だった。
先着していた救急隊は、私たちと入れ替わりですでに下山している。ここから先は引き継いだ警察の仕事になるが、山中に臨場したのは私と若手刑事だけだった。つまり、たったふたりで遺体を担ぎ上げ、ふもとの駐車場まで山道を下っていかなければならない。考えただけでも気が遠くなる作業だが、ここまで来たらやるしかない。私は額の汗を手の甲で拭うと、覚悟を決めた。