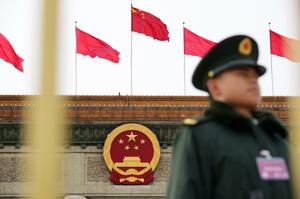堀越さんは現在、伊豆長岡にお寺を構えている。私は数年に一度、長井さんの命日近辺に堀越さんを訪ね、お経をあげてもらっていた。前回から結構間が空いてしまったので今年は伺おうと思い連絡を取った。自然に長井さんとの昔話に花が咲いた。
「先入観を持たずに現地の人々と話して、するっと懐に入ることができる人だよね。そんでもって正義感はとても強い。人に好かれるから、ふつうだったらインタビューできない人もツテで取材できたし、取材時はそういう重要な人とわかってなくても後々スクープだったりして。気鋭のジャーナリスト的な尖ったところはまるでなくて、そこはどうなんだと思うけど、みんなからおだやかないい人だと思われていたよね。ただ、近い人しかわからないと思うけど『癇癪持ち』だったよね」
本当にその通りで、私にとっては現地の人とのコミュニケーションの取り方はとても参考になったし、癇癪からは忍耐と辛抱を学んだ。長井さんを思い返すとき、真っ先に浮かぶのが破壊されたパレスチナのジェニン難民キャンプで現場を見つめる長井さんの写真だ。厳しくありのままを映し出そうとする決意が宿る瞳。私と長井さんに共通点はあまりないが、「ありのままを映(写)し出そうとする」姿勢だけは同じだったように思う。
残された映像に滲み出るプロの矜持
最近、あらためて長井さんの映像をネットで探して見てみた。イラク戦争を撮った作品の中に、アンマン-バグダッドハイウェイ道中の映像がある。たまに入っているシャッター音は私のものだ。記憶はあるが、あの時の空気や雰囲気、話したことなどディティールは風化している。だけど映像は残っていて、確かにあの時私は長井さんと一緒にいたのだ。そして映し出されるバグダッドの街、戦争で犠牲になった子どもたちの姿。難病の少年、サード君のためにオムツを買い付ける様子もあった。映像は今のものに比べて粗く、セピア色の写真を眺めているような懐かしさがあった。
あれから時代は大きく変わった。誰もがスマートフォンを持ち、世界中のどこからでもポストできるようになり、ホームページからブログ、そしてSNSへとブームは移った。SNSもすでに終わったという人もいるが、ニュースは速い。そして個人の連絡手段としての電話やメールはほぼ皆無となり、MessengerやWhatsApp、日本ではLINEが主流に。スマートフォンがあれば質はともかく誰もがレポーターになるし、だからこそフェイクニュースも多い。今やテレビや新聞といったオールドメディアと呼ばれるものたちはそこからネタを拾う始末だ。だから「あ、それ昨日見た」、ということが多い。若者はテレビさえ見ず、自分の好きな時にYouTubeなどを見る。そして今年に入ってコロナ禍でそういったイノベーションが一気に加速した。
人々の感情や情景を丹念に拾い、情熱と神経を傾けて編集したものを作品として放映する、ということは撮って出しのような映像と違って朝飯前にできることではない。そこにはプロとしての矜持がある。長井さんが生きていれば今どんな作品を撮っただろう。スマートフォンをジンバルに装着して、あの大きな顔を自撮りしながらレポートしていたかもしれない。そしてアプリで編集して配信したかも。そんな楽しい想像を話しに、堀越さんを訪ねようと思う。
あらためて合掌、14回忌の前に
 長井さん。アンマンのダウンタウンで(写真:嘉納愛夏)
長井さん。アンマンのダウンタウンで(写真:嘉納愛夏)