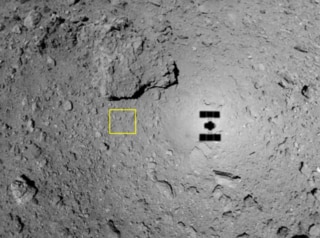国際宇宙ステーション「きぼう」から語りかける宇宙飛行士の山崎直子と野口聡一(写真:ロイター/アフロ)
国際宇宙ステーション「きぼう」から語りかける宇宙飛行士の山崎直子と野口聡一(写真:ロイター/アフロ)
(文:西野 智紀)
1983年、知的欲求旺盛なあるジャーナリストが一冊の本を上梓した。それは、米ソが宇宙開発戦争に明け暮れていた時代、母なる地球を離れ、宇宙へと向かった飛行士たちの精神的変化に着目し、幅広い知識をベースに、インタビューイを搾り尽くさんばかりに貪欲な取材を重ねまとめ上げたノンフィクション――立花隆『宇宙からの帰還』である。
人類は今の地上の支配者だ・・・と書いても過言でないと思うが、その支配地全景を外側から見た者はほんの一握りだ。暗黒に浮かぶ地球を肉眼で見るとは。地球の美しさとは。そして人生観を一変させてしまうかもしれない宇宙体験とはどのような感覚なのか。
この本の発表から四半世紀以上が経ち、今ではアメリカとロシアだけでなく世界各国から宇宙飛行士が誕生した。日本からは現在までで12人が宇宙へと飛び立った。この日本人宇宙飛行士たちに、立花氏と同じ着眼点から取材を敢行したのが本書である。著者は1979年生まれのノンフィクション作家で、10代の終わりにこの著作を読み感銘を受けたそうだ。
「ドライな印象」は宇宙が身近になった証拠
本書の読後感をまず述べると、『宇宙からの帰還』に登場する飛行士――伝道師に転向したジム・アーウィンや精神を病んでしまったバズ・オルドリンなど――と比較すると、日本人飛行士たちは宇宙体験に対してややドライな印象を受ける。それに合わせてか、書き手の熱量も格段に落ち着いたものとなっている。これは、もとより日本人は宗教観が薄く、神という存在の捉え方が違うところに起因しているのだろう。が、それよりも、冷戦終結、飛行士の増加といった時代の変化で、宇宙が身近な空間となりつつあることを示しているように思える。
とはいえ、各々が宇宙飛行の前後で芽生えた感情、感慨を語る場面となると、不意に熱がこもってくる。日本人初の宇宙飛行士である元TBS記者・秋山豊寛は、宇宙ステーションで90分に一度やってくる夜明けの時をこう語る。
「太陽が地表のすれすれを照らし出すとき、恐らく青い波長の光が最初に拡散して、次の赤い波長の光だけが最初に残っているんだと思うんだけれど、水平線というか地平線に当たる部分が本当に深紅に輝くんですよ。で、『あ、夜明けだ』と思った瞬間、深紅に染まった縁の部分が一気に真っ白になる。(略)本当に様々な色の全てが音になって、心地よい音楽のように自分の身体に入ってくるような気がしたんです」