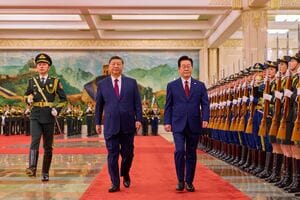結局二人で相談して、リスクは指摘するものの、本心とは離れたマイルドな言葉に置き換えたのだ。いまから思えば意思を曲げることにつき合わせた同期には申し訳ない気持ちでいっぱいだ。その後、当時はあり得ないと思われた倒産が連鎖的に発生し、業界を越えて日本は失われた20年に突入していった。
欧米企業の個性重視は生き残り戦略の一つ
バブルの渦中で働いていた状態を何かに例えるとすれば、夜の二次会、三次会で泥酔しながらカラオケに夢中になっているようなものだ。
私は酒が弱いのでより強く実感するのだが、ウーロン茶を飲んでいても自分を酔わせて気持ちを高めていかないととてもついていけない。「そろそろお開きの時間ですね」などと冷静なことを言えば、「つまらないやつ」として弾かれていくわけだ。
不動産融資業界についても同様だった。いま思い起こすと、“業界常識”のおかしさに気づいたのは、新人のわれわれだけではなかった。不動産上昇神話の異常さを指摘する人はどの企業にも複数存在していた。しかし、彼らは一人、そしてまた一人と、エリート路線から外されていった。
正論を吐きながらも出世できるのはごく一部の天才だけだ。私も含めて大勢は、何かに気づいても、それを上手な言葉に直して発信していかないと消えていくだけだ。だから、物事には言い方がある・・・そんなことをずっと若手・後輩たちには助言してきた。
しかし一方で、「感性も鋭くて、発信の仕方も上手な人なんて、いったいどれだけいるんだろう?」とずっと疑問にも思ってきた。
その後、外資系金融機関社長となってみて、自分の疑問は確信に変わった。グローバルビジネスの現場は、サバンナのサファリパークのようなものだった。個性爆発、自分の信じるままに思いを発信し、ぶつけ合う場だった。マネジメントの役割は、「言い方を直したほうがよいぞ」と指導することではなかった。求められるのは、「言い方はともかくも面白いことをいうなぁ、変なことをいうなぁ、なぜそんなことをいうの?」と質問する力だったのだ。