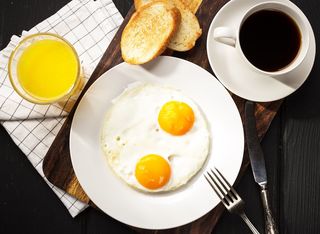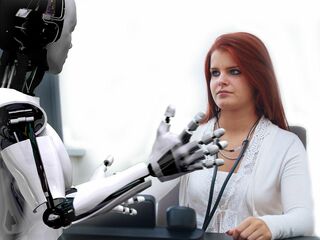コクは3つの要素でつくられている
「コク」というと、かつてビールのCMに使われた「コクがあるのに、キレがある」というフレーズが思い浮かぶ。ビールのほか、コーヒーやワインなどの飲料、シチューにラーメン、乳製品など多くの食品で「コク」という表現は使われる。
このようにコクはよく使われる用語だが、実は科学的にはコクの実体はよく分かっていなかった。コクを研究する女子栄養大学教授の西村敏英さんは、「『コクという味がある』とよく誤解されるのですが、そうではなく、コクは味や香り、食感が一体になった総合的な感覚です」と説明する。
そして西村さんらは、「コクは、味や香り、食感による多くの刺激(複雑さ)で形成されるものであり、それらの刺激により広がりや持続性が感じられたときの味わいである」という定義を提案した。
つまり、コクは、「複雑さ(深み)」「広がり」「持続性」の3つの要素でつくられるのだという。
複雑さは、風味のベースとなる味成分や香気成分によるものである。これらの成分が多くなればなるほど、風味は複雑になり、深みが出る。長時間煮込んだ料理や発酵食品にコクがあると感じるのは、調理加熱している間や発酵の間にどんどん食品成分の化学反応が進み、新たに多くの味成分や香気成分が生じるためである。
たとえば、肉を煮込むと、タンパク質は分解し、生成したアミノ酸やペプチドがうま味成分になる一方、アミノ酸や糖などの成分どうしが反応して新たな香気成分が生じるなどして、どんどん成分が増え、複雑になる。
また、広がりは、これらの複雑な刺激が口の中で広がる感覚である。そして、持続性は、口の中でこれらの食品の刺激が長く残っている感覚である。
風味が複雑なほど、そしてこの風味が口の中に広がって長く残れば残るほど、コクを強く感じるというわけである。