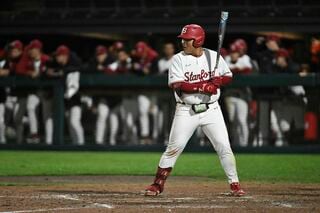車両にかかわる人が、電気系の仕事をすることは少ないですし、土木系の現場に属す人が、駅で働くこともありません。たとえば国鉄では、機関車を実際に運転する乗務員が属している現場と、機関車の運用計画を担当している箇所はまったく別であり、相互の意思の疎通さえも難しいものがありました。
つまりは、鉄道にかかわっている1人、1人の「鉄道人」は、あくまでシステムのごく一部の仕事を担っているにすぎず、むしろ一生かかわらない仕事のほうが多かったのです。
「鉄道魂」を感じた地滑り事故
しかしその後、鉄道を支える人々の「鉄道魂」を再認識できる事件にも出合いました。それは1957年、愛知県と長野県を結ぶ飯田線の「大嵐(おおぞれ)―小和田(こわだ)」駅間で発生した地滑り災害のときでした。
トンネルと鉄橋が押し流され200、300メートルもの区間、線路が跡形もなく消えてしまうという大規模な災害で、長期運休はやむをえない状況でした。ただ、同地には鉄道以外に連絡方法がない集落が多くあり、一刻も早い代替手段の手配が望まれました。そこで検討の結果、不通区間を天竜川(てんりゅうがわ)の舟運で結ぶことになりました。
ダムの保守管理用に電源開発会社が保有している巡視船を借り、乗客を乗せて運航する資格をもつ青函鉄道連絡船の船員にわざわざ来てもらい、乗客の足を確保したのです。不通区間の両端の駅には仮桟橋と通路を整備して、乗り換える乗客を案内しました。
私も案内係として大嵐駅に2回派遣され、その際、国鉄職員同士の強固なチームワークを感じるに至ったのです。異常事態ですから、さまざまな部門の職員が普段は互いに壁を築いている系統や所属を超えて集まってきます。
そこでは、私のような営業職員が資材運搬を手伝ったり、工務を担当する職員が旅客を案内したりもしました。肩書きの違いも労使対立もなく、ただ乗客のための一刻も早い復旧と代替手段の確保を目指しました。現場を激励に訪れた局長は、1人、1人の職員の手を握って慰労の言葉をかけ、なかには感激して泣いている人もいました。