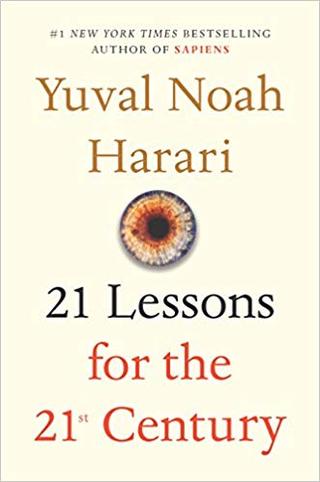米政府やバチカン、モサドも実はナチスを助けていた
こうした事例を挙げながら、オライリー氏が本書で明らかにしている事実の中で興味深いのは以下の点だ。
1つ目は、米政府がナチスの残党を捜査するイスラエル政府や関係組織に積極的に協力しなかったところか、残党を諜報部員として雇っていた時期があったという事実だ。
その実例として挙げているのが、「リオンの虐殺者」の異名を持つクラウス・バルビー元ナチス親衛隊員を対ソ・スパイに使うために雇っていたケースだ。
2つ目は、ローマ法王庁、特にピウス12世のナチス容認外交についてだ。
同12世は1933年、ヒトラー政権下のドイツとライヒスコンコルダート(政教条約)を結び、ナチスにお墨つきを与えてしまった。
理由は、ドイツ国内のカトリック信徒の保護やカトリック系学校や施設を迫害から守るためだった。
しかし、ナチスのユダヤ人迫害を欧州本土に拡大する中でも批判せず、「不偏」を貫いた同12世の対応は許しがたいというのがオライリー氏の主張だ。
3つ目は、ナチス親衛隊特務部隊員だったオットー・スコルツェニーについてだ。
スコルツェニーは、イタリアのベニート・ムッソリーニ首相(当時)を救出、1944年、ナチス郡の最後の大反攻となったアルデンヌ攻勢の陣頭指揮を執った男だ。
米政府をはじめ連合国は、スコルツェニーを戦後も捕らえ切れず、南米に元SS隊員たちによる「基地」を作られてしまった。
この「基地」を拠点に南米に次々と反共独裁政権を樹立させた立役者にしてしまった。
それだけでなく、イスラエルの諜報機関モサドはスコルツェニーを同機関の一員として徴用したというおまけまでついている。