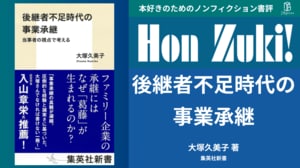距離感というのが自分にとって一番大事だということは、逆をやってみてわかったんです。自分の本を4冊ぐらい出したんだけど、ほとんど売れない。なんでベストセラーの方程式を持っている人間が、それを使えないんだ、と。結局、自分で思い入れがある本は売れない。売ることに携わっている人間が、距離感を崩してはいけないと実感した。その距離感さえうまくいくと、それだけ商品(本)がうまく見える。きっとこれ売れますよ、って言えて、なんとなく当たる。長いことやっているからそうなるんだけど。
あくまで装丁はビジネスだと思っている。10の中で7~8がビジネスなんです。自分の思いみたいのが2~3割。最近の編集者は自信もないし経験も少ないから、その場で決められない。こっちが提案しても「わかりました。社に戻って会議にかけてそのあと返事をします」ってそれじゃ普通の会社だろという感じになっちゃう。以前は全部任されていて「よし、これでいきましょう」という人がいたんだけど、今はどんどん少なくなっている。
会議というのは、「ひとこと言っておかないと」と言わなくていいやつが余計なことを言う。本ってみんなの意見を聞いて民主主義でやればやるほど売れなくなるんだよ、と教えるんだけど、伝わらない。刺身みたいなもので、活きのいい状態にちょっとひと工夫加えるだけで出すとヒットにつながるんです。
折原 以前は編集者と装丁家と、あとはイラストレーターさんとか写真家さんとか、それぐらいで作られていたところがあったんですが、最近は営業の方も発言権がありますし、さらに書店さんの意見を聞くこともある。みんなの意見を合体させればよくなるというわけではないところに難しさがあるという気はします。
坂川 以前やっていた広告の仕事の最初のころに、自分が商品の詳しい構造をあまり知らないということが先方の社長にばれてしまったんです。そのとき30代かな。打ち合わせをしているときに「坂川くんはうちの商品のことをあまりわかっていないみたいだね」って言われて。そのときはすごくあせったけど、とっさにこういうことを言った。全部を知っている人はいないといけない。ただ僕の場合は消費者の部分を半分ぐらい残しておきたい。本の場合、編集者は4回ぐらい読み直したりして、そうするとどう売ればいいかがわかんなくなっているんです。「こんないい作家なのでたくさん売ってください」で終わりになっちゃう。つまり意識全部が売り手側に回ると、消費者の部分が見えなくなる。それが怖いって。その場ではあまり納得してもらえなかったけど、仕事は10年ぐらい続きました。
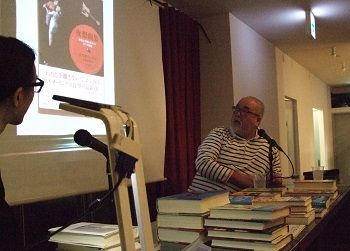 これまでに装丁した数々の本を見せながら解説する
これまでに装丁した数々の本を見せながら解説する
自分はデザイナーとしては二流ぐらいなんですが、売ることに関してプロなんです。そこに尽きます。
折原 では、その距離感を保ちながら、売れる本をデザインするためには何が必要なんでしょうか。
坂川 仕事をやるときに一番大事にしているのは、時代の潮目を読むこと。いい時代を生きてきたと思います。1960年代とかから始まって、価値観がすごく多様化して揺れ揺れになっている時代まで全部味わってきた。最初は世代的にアメリカ指向で、全部アメリカがいいと思っていたんですけど、今はなんか嫌いになっちゃった。ヨーロッパとか違う世界の方がおもしろい。