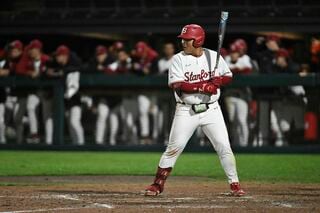コンピュータ予測は当たらない
IPCCが語る気温の「怖い」上昇も、影響(海面上昇、氷河の後退、海氷の減少)も、大半が「コンピュータの予測(シミュレーション)ではこうなる」という話だった。
「2100年に気温がこれほど上がる」「海面がこんなに上がる」といった予測をメディアが鵜呑みにして流すため、政治家から幼稚園児まで全員がおびえる仕掛けになっている。
気温については、「気候感度」の評価が核心をなす。気候感度とは、「CO2濃度の倍増で気温が何度上がるか」を示すものだ。IPCCは2007年の報告書で「気候感度は1.5度~4.5度。1.5度未満は考えにくい。いちばん確からしいのは約3度」と述べた。
しかし気候感度をいくらと見るかはまだ異論が多く、昨今もいろんな見解の論文が出る。IPCCは、最低に近い値を「確信度が低い」のだと退けてきた。
CO2濃度の将来動向も読みにくいため、IPCCは複数の排出シナリオをもとにコンピュータ計算している。今回の報告書は、シナリオ4種の結果をまとめ、2100年に最高4.8度、最低0.3度と見積もった。それを受け、日本のマスコミは「今世紀末に地球の気温が4.8度上がる」と危機をあおりたてている。むろん、IPCCは「0.3度なら心配はない」とか、「最低値になるよう期待する」といった表現をすることはない。
気候システムは複雑きわまりない。仮に温暖化が進めば、海水の蒸発が増える。結果として増える雲が、温暖化を加速するのか(正のフィードバック)、抑えるのか(負のフィードバック)も不明だ。
IPCCは「正のフィードバック」派だが、かつて大気中CO2濃度が現在の4~5倍だった1億年ほど前、地球が熱暴走した証拠はない。そうである以上、負のフィードバックが正解ということになる。要するに気候の計算はまだ完成していない(50年後もそうだろう)。
いま気候モデルの数は70を超すという。正しい答えを出せるのか(それとも出せないのか)は、過去~現在の実測値とシミュレーション結果を比べれば分かる。比較をした結果、ほぼ全部のモデルが実測値と大きく外れたことが明らかになっている。
IPCCはその比較もしたけれど、報告書に載せた図(番号1.4)では、比較用の基準年を巧みにずらし、外れの度合いを小さく見せている。
だがそんな小細工がいつまでも通りはしない。気温低下が今後も続けば、言い逃れできない瞬間が絶対に来る。だから「次回のIPCC報告書はない」と見る人も多い。
ちなみに夏の北極の海氷面積は、IPCC予測を尻目にここ1年で60%も増え、過去10年間の最高を記録した。そんな事実が、温暖化科学の未熟さを語り尽くす。