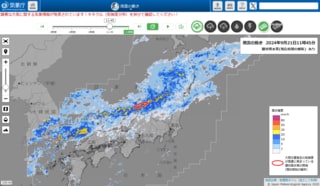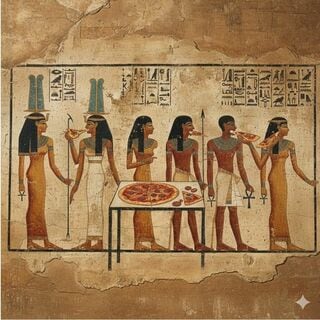空襲で焼け野原になった東京(提供:U.S. Air Force/AP/アフロ)
空襲で焼け野原になった東京(提供:U.S. Air Force/AP/アフロ)
1920年代に結ばれた国際条約は、日本の外務官僚たちに「日本は不利な立場に置かれている」と感じさせ、彼らの「被害者意識」を呼び覚ました。この意識はやがて他国を排除する対中政策へとつながり、「東亜新秩序」の構想は「大東亜共栄圏」へと拡大していく。そして、泥沼化した日中戦争継続のため、日本は無謀ともいえる太平洋戦争へ突き進んでいった。
相手を理解し、尊重する「寛容性」を失った外交政策が、いかに国家を破滅へと導くのか。『外務官僚たちの大東亜共栄圏』(新潮社)を上梓した熊本史雄氏(駒澤大学文学部教授)に話を聞いた。
──本書には、1920年代、日本の外務官僚たちには「国際連盟規約」(1919年6月署名)、ワシントン会議での「九カ国条約」(1922年2月調印)、「不戦条約」(1928年8月締結)に対する理解が不足していたとあります。
熊本史雄氏(以下、熊本):1922年のワシントン会議は、第一次世界大戦後のアジア太平洋地域の新秩序を築く重要なものでした。
九カ国条約ではアメリカ、イギリス、日本などが中国の主権と領土保全、「門戸開放」政策の維持を確認し、四カ国条約では米英仏日による太平洋地域の現状維持と列強間の紛争防止が目的でした。
当時は、これらの条約によって世界秩序が保たれると多くの外交官が信じており、日本も例外ではありませんでした。ところが、現実には中国は統一されておらず、国民党と共産党が争う混乱期で、ソ連も条約の当事者ではありませんでした。けれども、1920年代後半には、列強の想定外の勢力が台頭し始めます。
さらに中国は、九カ国条約の「門戸開放・機会均等」の原則を逆手に取り、これを自国の利益に活かす方向で動き出しました。条約の条文を戦略的に解釈し、独自の外交カードに変えていったのです。
このように、条約の精神を素直に受け止めていた日本の外務官僚たちにとっては、予想外の展開でした。結果として、「列強が協調すれば新たな秩序を築ける」という前提が崩れ、1920年代後半には秩序維持が難しくなっていきました。
──九カ国条約の運用については、日本以外の列強も同様に見通しを誤っていたのでしょうか。
熊本:たとえば、米国も当初は九カ国条約がその後の国際秩序形成にこれほど大きな意味を持つとは考えていなかったようです。実際、当時の政府高官の発言を見ても、それほど重視していた形跡はありません。
しかし1920年代を通じて、「中国をどう扱うか」が国際政治の重要課題となっていきました。九カ国条約は、中国の領土保全と門戸開放、すなわち他国と平等な通商の機会を保障するものでした。
その中で、九カ国条約による通商の束縛を最も大きく感じたのは、日本でした。
イギリスやフランスは中国から地理的にも歴史的にも距離があり、本国から遠く離れた植民地を数多く持っており、中国における各種の利権もそうした性格のものでした。米国も自国内に広大な資源を抱えており、中国市場が多少制限されても深刻な影響は受けません。
一方で日本は、中国や満州がほぼ唯一の資源供給地でした。つまり通商をはじめ借款などの投資政策における中国の重要性が、他国とは比べものにならないほど大きかったのです。九カ国条約によって中国での経済活動が制約されることは、日本にとって死活問題でした。
──条約体制への不満は、その後の外交方針にも影響を与えたのでしょうか。