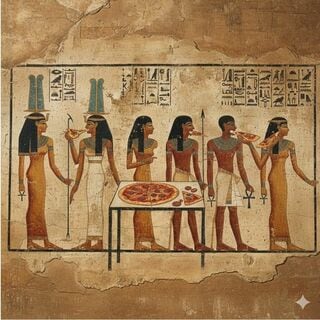日本の収支構造は、貿易収支が赤字でも第一次所得収支で黒字を出せる構造に変わった(写真:ロイター/アフロ)
日本の収支構造は、貿易収支が赤字でも第一次所得収支で黒字を出せる構造に変わった(写真:ロイター/アフロ)
円安はいつまで続くのか。日本の経常収支は黒字続きであるにもかかわらず、なぜ、円高に転じないのか。
円安の背後では、日米の金利差や海外での投資収益、増え続けるデジタル赤字など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていると語るのは石川久美子氏(ソニーフィナンシャルグループ株式会社 シニアアナリスト)。『円安はいつまで続くのか 為替で世界を読む』(マイナビ出版)を上梓した石川氏に、今後の円の行方について、話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
──新型コロナウイルスのパンデミックによって加速したインフレに対し、欧米諸国の中央銀行は比較的早い段階で利上げを敢行しました。一方、日本銀行(以下、日銀)が利上げに踏み切ったのは2024年3月。この間に生じた「金利の差」によって、円安が進行した可能性があると書かれていました。
石川久美子氏(以下、石川): 金利が高い国には資金が集まりやすいという傾向があります。
例えば、100万円を運用する場合を考えてみましょう。
日本の金利が0%、米国の金利が5%、為替レートが1ドル=100円だと仮定します。日本に預けても1年後の元本は100万円のままですが、ドルに替えて1万ドルを米国で運用すれば、1年後には5%の利息がついて1万500ドルになります。
さらに、その時点でドル高が進み1ドル=110円となっていた場合、これを円に戻せば115万5000円になります。
このように、信用力が同程度の国同士であれば、低金利の国よりも高金利の国で運用するほうが、金利収入に加えて為替差益も得られる可能性が高くなります。これが「金利が高い国にマネーが流れる」メカニズムです。そして資金流入はその国の通貨需要を押し上げ、結果として通貨高につながります。
──2019年末からのコロナ禍では、どのような影響があったのでしょうか。
石川:パンデミックの発生によって先進国ではサービス需要が急減し、景気が悪化しました。
それに対して、各国の中央銀行は利下げに踏み切り、金融緩和で対応します。その後、経済活動をいち早く再開した米国から景気が回復し、財需要の増加が賃金や家賃などのサービス分野にまで波及、インフレが加速しました。そこにロシアによるウクライナ侵攻が重なり、欧米は2021年末から利上げを開始しました。
一方、日本は長期にわたり低インフレが続き、企業がコスト上昇分を価格転嫁しにくい状況が続いていました。結果として、日銀の利上げ決定は2024年3月まで遅れ、その間に日米間の金利差が大きく開いたのです。
為替レートは大きな流れとして、名目金利から物価上昇分を差し引いた「実質金利」の差に左右されます。特に2021年以降は、ドル円相場が日米の実質金利差と非常に強く連動しており、この金利差の拡大がドル高・円安を一層進めたと考えられます。
──2022年1月に日銀が公表した展望レポート「経済・物価情勢の展望」では、実質実効為替レート(※)に10%の円安が加わった場合、1%弱程度実質GDP(国内総生産)にプラスの影響を与えると書いてありました。なぜ円安はGDPにプラスになるのでしょうか。
※自国通貨の価値を、複数の貿易相手国との為替レートと物価水準の差を考慮して示した指標のこと。