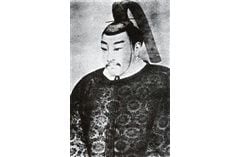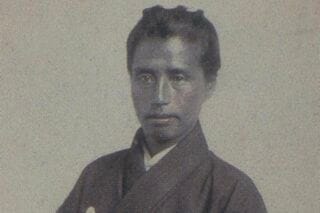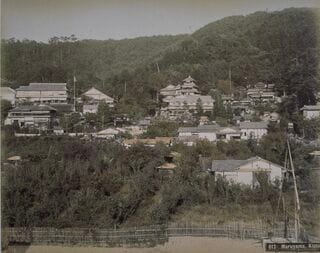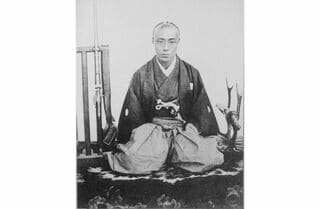容堂の策略と罠にはまった武市
 山内容堂
山内容堂
ギャラリーページへ
文久3年8月6日、容堂から招請があり、武市半平太は4時間ほど拝謁した。容堂は、武市に媚びるような態度を示し、人材登用を約して尊王攘夷の大義を吐露した。武市は油
残り1776文字
 山内容堂
山内容堂
文久3年8月6日、容堂から招請があり、武市半平太は4時間ほど拝謁した。容堂は、武市に媚びるような態度を示し、人材登用を約して尊王攘夷の大義を吐露した。武市は油
残り1776文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら