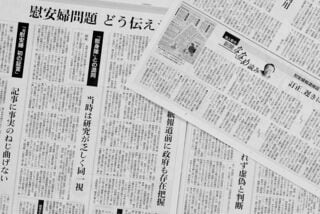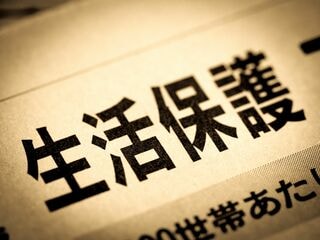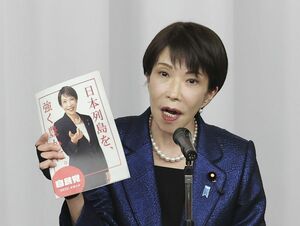2022年9月の台風で崩落した静岡県内の橋(写真:共同通信社)
2022年9月の台風で崩落した静岡県内の橋(写真:共同通信社)
真偽不明の情報がネット空間には溢れている。選挙や災害時には、デマや誤情報が混乱を招き、人々の重要な判断を狂わせ、時には深刻な対立の原因になる。私たちはどのようにして、この混乱した情報空間と向き合えばいいのか。『災害とデマ』(集英社インターナショナル)を上梓したジャーナリストの堀潤氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
啓蒙の意味を込めてフェイク写真を作成?
──この本では、災害報道に便乗する形でSNS上などに出回るデマについて書かれています。
堀潤氏(以下、堀):2022年9月に静岡で台風の影響で水害が発生した時に、生成AIで作った複数の写真がSNS上に出回りました。「静岡県の水害がやばい」といった調子で、街全体が濁流の中に浸かっている写真でした。実際に静岡で起きている水害が報じられていたために、こんなにひどい状況なのかと写真はどんどん拡散されました。
ところが、しばらくして「この写真はフェイクではないか」というコメントも見られるようになりました。するとなんと、生成AIを使ってその写真を作った人物が「そうです」「これは噓です」と公に認めたのです。
「このような災害のフェイク写真を作れる時代になったので気をつけましょう」という啓蒙の意味を込めて、こうした写真を発信したというのが彼の言い分でした。
私はまさにその時に、その水害の現場で取材しており、確かに街が水に浸かっていましたが、その写真ほどには浸かっていませんでした。その結果、水害の被害を受けた現場では、とてもねじれた状況になってしまいました。
というのも、場所によっては住民の首近くまで浸水したところもあり、さまざまな支援が必要な状況でした。ところが、フェイク写真が拡散されたことで、SNS上では「噓だったんでしょ」という言説が広がったのです。
結果的に、私たちが報道するときに、「確かに起こっているけれど、あの写真ほどではありません」という複雑な説明をしなければならなくなりました。
本当であればもっとたくさんのボランティアや行政の支援が入り、どれだけのサポートが必要か早々に検討されたはずなのに、フェイク写真の影響で余計な障壁ができて支援は遅れました。
こうしたことが起きたのは、これが初めてのことではありません。
震度7の揺れを観測した2016年の熊本地震では、「動植物園からライオンが逃げ出した」という画像付きのデマ情報が広がりました。私は、熊本市動植物園の職員たちがその後どのような目に遭ったのか追跡取材をしました。
動植物園には「ちゃんとライオンを管理できていなかった」と責める非難の声が殺到していました。本当だったら余震もあるし、すぐに避難すべき状況ですが、動植物園近くの住民の中には「怖くて外に出られない」と語る人もいました。
動植物園の職員たちは、動物のケアを含めて災害の対応に追われている最中ですが、同時にそうしたフェイク情報への対応にも追われたのです。
 当時のフェイク画像
当時のフェイク画像
──山ほど電話がかかってきたと書かれていました。
堀:その中には一方的な誹謗中傷もありました。