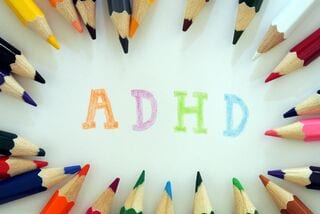自閉症スペクトラム症者には、多くの人が価値を見出さないようなものを集める傾向もある(写真:IZWAN IS/shutterstock)
自閉症スペクトラム症者には、多くの人が価値を見出さないようなものを集める傾向もある(写真:IZWAN IS/shutterstock)
「発達障害」という言葉はよく使われるようになったが、その意味はかなり広く、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)、発達性協調運動症(DCD)、チック症、吃音症など、症状の異なるものが含まれる。
しかも、複数の症状を持つ人もいるので、いろいろな要素が混同されて語られがちだ。こうした発達障害の要素を持つ人たちの中には社会に馴染めず、その人固有の苦しみや孤独を抱えていることが少なくない。
彼らはどのように異なり、なぜ孤独なのか。『「心のない人」は、どうやって人の心を理解しているか 自閉スペクトラム症者の生活史』(亜紀書房)を上梓した京都府立大学文学部准教授の横道誠氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
──本書では、7人の自閉スペクトラム症者へのインタビューを紹介しながら、それぞれの方の話に対して横道さんがどんな感想や考察を持ったのかということが書かれています。なぜこうした本をお書きになったのでしょうか?
横道誠氏(以下、横道):私の本業は文学研究ですが、5年ほど前に発達障害があるという診断を受け、そこから発達障害の問題に取り組み始め、そうした方々を支援する自助グループを運営するようになりました。
やがて本業の仕事と、そうした個人で行っている発達障害に関する取り組みを融合させる研究プロジェクトを立ち上げ、発達障害者に文学に関するインタビューをして、発達障害者が文学作品をどう読むかという研究をしています。
今回はさらにそれを発展させて、文学作品に限らず、様々な創作物からいかに発達障害者が影響を受けているのかを調べました。
教育心理支援教室・研究所「ガジュマルつがる」代表の松本敏治氏は、自閉スペクトラム症者は方言が苦手な傾向があると発表しました。その理由の1つとして、自閉スペクトラム症者は日常的なコミュニケーションが苦手なので、本や映像から言語を習得する傾向が強いと論じられています。
私はそこからヒントを得て、自閉スペクトラム症者は言語に限らず、本や映像作品から多くを学んでいるのではないかと考えました。
自閉スペクトラム症者は「他人の気持ちが分からない」「他者に対する想像力がない」「共感性が乏しい」と言われてきましたが、そうした弱点になりがちな部分を克服するために、創作物から人の心を学ぼうとしているのではないかという仮説を立てたのです。
そこで本書では、自助グループ活動やSNSを通じて知り合った当事者の方々にインタビューをして、本人たちが何を考えているか、いかに創作物から影響を受けてきたのかをまとめてみました。
──自閉スペクトラム症とはどのような症状や状態にある人なのでしょうか?