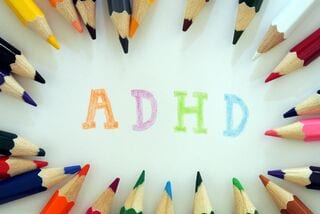運動することで、原始反射を整えることができる(写真:graphica/イメージマート)
運動することで、原始反射を整えることができる(写真:graphica/イメージマート)
発達障がいのお子さんは日常生活になんらかの「困りごと」や「トラブル」を抱えています。保護者の中にも、自分の子なのに育てにくい、ほかの子どもと比べて○○ができない、遅れている、発達障がいをはじめ何らかの障がいがあると診断された──など、不安を抱えている方が大勢います。
相談できる窓口も常に混雑していて予約が取りづらいという声がある中、家庭ではどのようにお子さんと向き合えばよいのでしょうか。発達障がいのお子さんの困りごとに運動療育という観点でかかわる松本哲さんの見解を見てみましょう。
※松本哲著・本間龍介監修『発達障がい&グレーゾーン 楽しく遊びながら子どもの「発達」を引き出す本』(青春出版社)から一部抜粋・編集しました。
その困りごと、実は子どもが一番困ってるんです
「すぐに癇癪を起こす」「落ち着きがなく座っていられない」「怖がりで一人でトイレやお風呂に入れない」「人見知りが強い」「こだわりが強い」「滑舌が悪い」「動きがぎこちない」「偏食が多い」などなど。
これらは、まわりから見ると問題行動であり、困った癖です。そのため、教室を訪ねてくるお母さん、お父さんの多くは、そんな子どもに対して、「困っています」と言います。
いままでずっと頑張ってわが子に寄り添い続けてきたのですから、その気持ちもとてもよくわかります。でも、その困りごと、実は一番困っているのは子どもなのです。
お兄ちゃんと弟のいわゆるグレーゾーンのきょうだいを連れて、見学に来られたお母さんがいました。自分ルールがあり、幼稚園でも小学校でも、友だちに注意をして回ってしまうと悩んでいました。
公的機関にも相談しましたが、「まだ小さいですし、暴れるわけでもないから様子を見ていればいいんじゃないですか」というようなことを言われ、ずっとモヤモヤした気持ちで過ごしていたそうです。