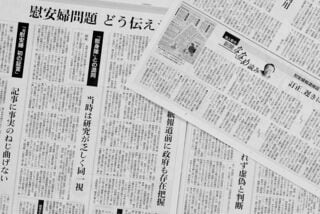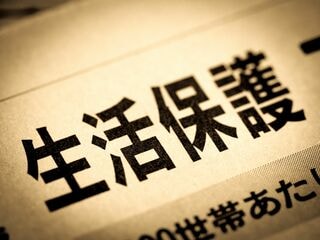フェイク写真を流した若者の「大義」
堀:逃げたライオンの画像は外国の写真を加工したものでした。その時に安易にフェイク画像を放ったのは神奈川県に住む二十歳の会社員の男性だということが明らかになりまし
残り3432文字
堀:逃げたライオンの画像は外国の写真を加工したものでした。その時に安易にフェイク画像を放ったのは神奈川県に住む二十歳の会社員の男性だということが明らかになりまし
残り3432文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら