再発見された「明智光秀寄進状」は本物か?改名の経緯からみる「明智光秀」という署名の“違和感”と“真意”
2024.12.27(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

ジャンヌ・ダルクは平将門に神の声を伝えた巫女と同種の存在であるということ
【歴史ノ部屋・連載】ジャンヌ・ダルク聖者の行進
シンクロナス編集部

「男色」に無関心だった豊臣秀吉は珍しかった?「とんでもない変人」と言われた秀吉の男色の逸話
江戸時代に「無体」と非難された男色、興味について「職業」は関係なかった?
乃至 政彦

なぜ伊達は上杉と同じ「竹に雀」の家紋を使ったのか
上杉の家紋を流用した伊達晴宗の事情とは【JBpressセレクション】
乃至 政彦
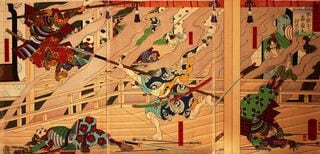
「男色」が広まったのは戦場からではない?今日的な同性愛とは異なる、戦国時代の男色にありがちな誤解
武田信玄と高坂昌信、上杉謙信と直江兼続、織田信長と森蘭丸の関係は史料の誤読か創作だった?
乃至 政彦

上杉謙信はなぜ景勝と景虎どちらも家督相続者に選ばなかったのか
「御館の乱」における上杉景虎の戦略(前編)【JBpressセレクション】
乃至 政彦













