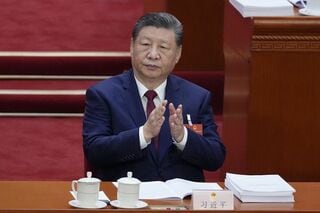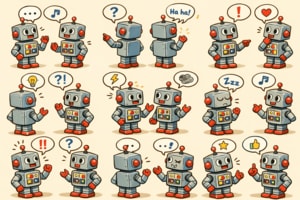東京・明治神宮外苑の再開発計画の見直しについて報道陣に説明する事業担当者=9月9日午前(写真:共同通信社)
東京・明治神宮外苑の再開発計画の見直しについて報道陣に説明する事業担当者=9月9日午前(写真:共同通信社)
明治神宮外苑の再開発計画が、また動き出してきた。事業者は9月、東京都に樹木の保全に向けた見直し計画を提出。東京都の小池知事は「都民の理解と共感を得られるよう事業者にしっかり取り組んでもらいたい」と応じた。イチョウ並木や環境への悪影響が懸念されてきた、この再開発計画。再開発は時に、文化的資源や景観、そこに暮らす人々の生活やコミュニティにも影響を及ぼしかねない。私たちは、これをどうとらえるべきか。人文系の研究者による解説を、2回にわたって紹介する(2回目/全2回)。
(*)本稿は『都市の緑は誰のものか』(太田和彦・吉永明弘編著、鬼頭秀一ほか著、ヘウレーカ)の一部を抜粋・再編集したものです。
>>第1回「2020東京五輪と神宮外苑再開発はつながっている…人と自然、文化財を破壊する“ジェントリフィケーション”の正体」から読む
(鬼頭 秀一:東京大学名誉教授)
いまの日本の「所有権」は特殊
明治以後に定められた近代日本の所有権の概念は、その土地を所有すれば、どのようにしてもいいという処分権まで含んだものとして捉えられている。しかし、明治以前においては、共有や総有などの考え方もあり、所有のあり方は重層的なものとして捉えられていた。
藩の所有地であっても、その地に暮らしている人たちにとって「入会権」という形で、何らかの利用権は設定されており、所有と利用のあり方は重層的であり緩やかなものだった。
グローバルに見ても、日本の近代的所有権はかなり特殊だといえる。現代の日本では、土地を持っていればどんな形の建物を建てても問題にならないが、欧米の住宅地では必ずしもそうではない。
また、近年では日本においても、所有と利用の問題をもっと緩やかな形で捉え直そうという機運があり、土地の所有のあり方は、建造物にしても自然生態系に関しても、公共的空間として周辺の人たちにとってのコモン(共有財)として、また社会的共通資本として捉えていくことが求められている。
イギリスにおける公共的な公園緑地の多くは王室や貴族の所有するものだったが、フットパス(歩く権利)の運動の中で、公共的空間として開放され、多くの人たちが憩うことができるものとなっている。
神宮外苑再開発問題も、明治神宮や三井不動産などの地権者が勝手にできるものではなく、風致地区にも指定されている公共空間としてのあり方は、より多くの人たちの議論でそのあり方を考えることが必要になってきている。
さらにいえば、ここには環境正義の議論も必要になる。この空間に関しては、歴史的にも関わりが深いさまざまなセクターの主体の協議や協働により、今後どのように管理していくべきかということを議論していくことも必要だろう。