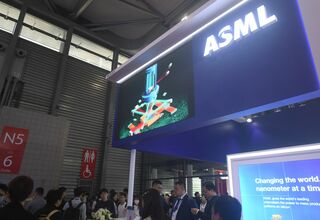移住者にも島出身者にも厳しい伊豆大島での生活
しかし居酒屋談義的に町で聞いた話は「地元で働きたくても仕事がない」「観光もダメ」など総じてなぜか暗い。よく考えてみれば、ある意味当然である。とても小さな町であ
残り2638文字
しかし居酒屋談義的に町で聞いた話は「地元で働きたくても仕事がない」「観光もダメ」など総じてなぜか暗い。よく考えてみれば、ある意味当然である。とても小さな町であ
残り2638文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら