『光る君へ』中国で「科挙」が発展したのは宋の時代、宋人が「戦に飽き飽きしていた」ワケとは?
2024.6.8(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

『光る君へ』清少納言に筆をとらせた定子の魅力、『小右記』につづられた兄・伊周との「意外な逸話」とは?
真山 知幸

『光る君へ』藤原道長の後半生、史上初の「一帝二后」を決行、念願の天皇の外祖父へ、晩年はどうなる?
紫式部と時代を生きた人々のゆかりの地(第20回)
鷹橋 忍

『光る君へ』紫式部の父・藤原為時は任地替えを自ら一条天皇に願い出た?数々の史料に書かれた逸話の「真偽」
真山 知幸

平安貴族の年収は?10年間無官だった紫式部の父・藤原為時はどう生活していたのか?
書籍『平安貴族列伝』発売記念!著者・倉本一宏氏に聞く平安時代のリアル(3)
倉本 一宏

『光る君へ』7歳で即位した一条天皇の生涯、寵愛したのは定子だけではなかった?詠んだ歌の「君」は誰をさす?
紫式部と時代を生きた人々のゆかりの地(第19回)
鷹橋 忍
本日の新着

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか
【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至
唐鎌 大輔

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)
髙城 千昭

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②
町田 明広

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙
木村 正人
豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
髙城 千昭
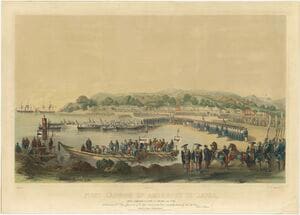
哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化
鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義
川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性
川岸 徹



