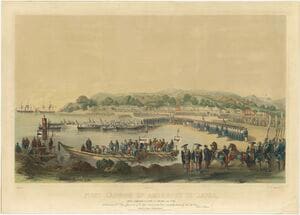本当の好きな人と…など現代人のメルヘン
 越前一乗谷の復原武家屋敷。当時の一般的な武士たちの暮らしが伝わる
越前一乗谷の復原武家屋敷。当時の一般的な武士たちの暮らしが伝わる
ギャラリーページへ
逆に、女子の立場で考えるなら、手頃な(身分家格が釣り合う)結婚相手に恵まれない可能性が高いことになる。それなら、たとえ百姓町人でも本当に好きになれる人といっし
残り774文字
 越前一乗谷の復原武家屋敷。当時の一般的な武士たちの暮らしが伝わる
越前一乗谷の復原武家屋敷。当時の一般的な武士たちの暮らしが伝わる
逆に、女子の立場で考えるなら、手頃な(身分家格が釣り合う)結婚相手に恵まれない可能性が高いことになる。それなら、たとえ百姓町人でも本当に好きになれる人といっし
残り774文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら