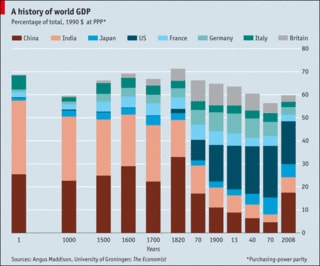前述の古典派経済学のリカードは、貿易に関して「比較優位」という重要な考え方を示していました。これは経済主体となる各国はそれぞれ最も得意とする分野のものの生産に特化・集中することが互いのメリットになるという考え方です。例えばA国はバナナをつくる、B国はハイテク製品をつくる、C国は綿製品をつくるという具合に国際分業を進めれば、それぞれ生産性が上がるし、そこで生産されたものを互いに貿易で取り取りすれば各国とも経済的利益を最大限に得ることができるという考え方です。
これにドイツ歴史学派の人々は、多少私の解釈も含めて説明すれば「いや、バナナをつくっている国だっていずれはハイテク製品や自動車をつくりたい。農業→工業という具合に、産業が進歩・発展していくことが国民経済にとって極めて大事なのだ。そのためには国家が積極的に産業育成をするべきだ」と主張したわけです。
このドイツ歴史学派とほぼ同時期はマルクスも登場してきます。リストの主著である『政治経済学の国民的体系』は1837年に出ていますが、マルクスとエンゲルスの共著である『共産党宣言』の出版年は1848年です。マルクスは資本主義を主張したわけではありませんが、国家が主体となる計画経済を唱えました。この時期は、経済に国家が介入するという考え方に振り子が振れていたのです。
経済学の歴史を飛び越えた「全く新しい」資本主義の提示は事実上無理
すると今度は、その考え方に対抗するように、19世紀後半から、新古典派経済学(ネオ・クラシカル・エコノミクス)と呼ばれる学説が登場し、主流となっていきました。メンガー、ジェヴォンズ、ワルラスといった学者らがこのグループです。オーストリア学派やケンブリッジ学派、ローザンヌ学派と少し細かく分類されますが、いずれもアダム・スミスの考え方をベースに、限界効用の考え方を用いて、それをさらに数理的に説明しながら、経済活動はマーケットに任せていこうと主張しました。
この考え方が経済学の主流になりましたが、不幸にもそこに大不況(世界恐慌など)がやってきます。不況は、市場における価格や数量調整メカニズムの不全が原因であり、長期的にみればマーケットの混乱は、新古典派が言うように、「いずれは収束する」と考えられなくはありません。しかし、「長期で言えば、人はみないずれは死ぬ、みたいな話を説いても仕方ない。嵐はいずれ収まる、と言っても今、困っている人民を救うことにはならない」と登場したのが有効需要の重要性を説いたケインズでした。不況の際には公共事業などを通じて政府が需要創出に積極的に動くべきだという考え方です。
ご存じのようにケインズ経済学は絶大な影響力を持ちました。しかし1970年代ごろになると、アメリカで今度は「新しい古典派」(ニュー・クラシカル・エコノミクス)と呼ばれるいわゆるミクロ経済を重視して、合理的な個人をベースにマーケットを重視する考え方が主流になります。私がアメリカに留学していた2001年当時でも「もうケインジアンの時代は終わった。(ケインズ経済学の用語である)非自発的失業とか言ってるのは誰だ?」という雰囲気が色濃くありました。
しかし2000年代にリーマン・ショックが起きると、今度は世界的に財政政策による需要創出の重要性や、即時的金融緩和が説かれるようになりました。ハーバード大学の学長や財務長官を務めたローレンス・サマーズは、当時「いまは全員がモデレート・ケインジアンだ」と発言していたほどです。それほどリーマン・ショック時に経済学の潮流はケインズ経済学に振れたのです。
このように資本主義と経済学の歴史を遡ってみれば、その時々の経済状況に合わせ、自由放任で行くか、政府の役割を重視するか、この2つの間で揺り戻しを繰り返しながら、議論されてきたことが分かります。