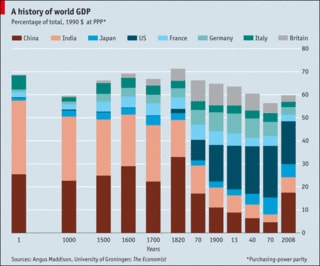来春、より本格的なビジョンを「新しい資本主義実現会議」での議論をもとに出していくということなので、そこに期待したいと思いますが、少々厳しいことを言えば、本来なら岸田首相が政権をとる前から、国民の多くがイメージできる「新しい資本主義の大きな方向性」くらいは少なくとも準備しておくべきものだったと思います。
ということで、これから本格的に中身が詰められることになる「新しい資本主義」ですが、私が想像するに、最終的にはせいぜい「古くて(やや?)新しい資本主義」に落ち着くことになるのではないでしょうか。なぜそんなことを言うのかと言えば、資本主義に関しては世界的にも歴史的にも、すでに相当な議論が尽くされてしまっており、それを超えるような「新しい」概念を打ち出すというのはかなり高いハードルになるからです。
経済学の歴史には法則性がある
もう少し詳しく説明してみましょう。
まず、資本主義について考えてみます。といってもこの文脈では、「資本主義の解釈の歴史≒経済学の歴史」と考えてほとんど差支えないので、経済学の歴史を振り返ってみたいと思います。
先に結論を言ってしまうと、歴史を振り返れば、その時々の経済学の主流というのは、「経済的な欲望を抑制せず、マーケットを信じて、自由な経済活動を推し進めていく」という考え方と、「規律を重視し、政府がある程度の権限を行使して経済活動を仕切っていく」という考え方との間で、振り子のように揺れ動いてきたことがわかります。
「経済学の父」アダム・スミスから見てみると、彼は『国富論』を著しましたが、この著作の主題は「重商主義へのアンチテーゼ」でした。それまでの経済学というのは王室経済を栄えさせるためのもので、輸出を奨励しつつ輸入は抑制するという貿易差額主義に代表される「重商主義」が主流でした。
それに対して、アダム・スミスは国民経済を重視しました。レッセ・フェール(自由放任)による経済活動を進めていれば、市場では「見えざる手」が働き、社会全体の利益になるという考え方です。
株の仲買人だったデヴィッド・リカードは、アダム・スミスの著作に影響され、経済学者に転身します。彼も『経済学および課税の原理』を出し、算数的に、比較優位を持つ産品に特化した国家同士が自由に交易することが全体の厚生を向上させることを証明し、経済学の一大潮流を生み出しました。このアダム・スミスやリカードの考え方が、いわゆる古典派経済学です。こうして経済学の主流派は、それまでの王室による統制経済を重視する重商主義から、市場メカニズムや自由貿易を主張する古典派経済学に大きく振れました。
この自由貿易の考え方に対して、「いやいや、国家がちゃんと市場に介入して産業を育成していくべきだ」という人々も出てきました。ドイツ歴史学派のフリードリッヒ・リストらが代表選手です。リストは、18世紀後半からの産業革命で大躍進したイギリスのような先進国に対して、ドイツのような後進工業国が国際貿易で力を発揮するようになるためには、まずは国家が介入して国内の工業を盛んにしなければならないと主張したのです。