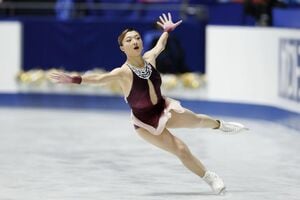「ライバルと言うには勝ち過ぎていた」
名勝負を演じたレスラーたちの声も示唆にとんでいた。
“覚醒前夜”と言える、ジャパン・プロレスとの対抗戦時代――あの長州力との60分フルタイムだ。当時の試合展開を徹底検証し、長州自身にも大学のレスリング時代の思い出を聞いた。
印象的だったのが、長州は呼び捨てではなく、先輩として敬って「鶴田さん」「鶴田先輩」と呼びながら、ポツリポツリと語ってくれた。
そして天龍源一郎。鶴田を「怪物」へと引き上げた「鶴龍対決」はファンにとっても忘れられない一戦だ。
「ジャンボ鶴田がライバル? いや、ライバルと言うにはジャンボのほうが勝ちすぎていたよ。だから俺からライバルって言うと口幅(くちはば)ったい。戦友がピッタリ来るのかな。全日本プロレスで一緒に戦っている時には、仲間という気持ちもあったから『お互いに生き抜こう』って思ったし、何かがあると『生き延びてほしい』『あいつが頑張ってるんだから、俺も頑張ろう』って思ったしね。もしライバルだと言えるとしたら・・・俺が全日本を辞めて別れてからのほうがライバルだったね。全日本にいた時は戦友だったけど、別れたあとは『生き様でジャンボに負けたくない!』って意識してたよ」
そこにはさまざまな感情が含まれている。ひとことで言い表すことができないのが、鶴田と天龍の関係だった。
三沢光晴、川田利明、田上明(のちに鶴田とタッグを結成)、小橋健太(現・建太)、菊地毅ら超世代軍との戦いを通して、「完全無欠のエース」に君臨した時代の男たちの言葉には惹きつけられるものがある。
「あの人に作戦どうのこうのは通じないんだね。最初からガーッと行くぐらいでちょうどいい。あの体質、スタミナ、スピード……あれが何年経っても落ちないのが不思議なんだよね。でも、あの人が怪物だから倒し甲斐があるんだよね。バケモノを倒してこそ、頂点を極められるんだと思うよ」(三沢)
「下手したら、笑いながら試合してんじゃないかっていうぐらい余裕があったよね。何か、ホントにね、オモチャにされているような感じがしたね。普通は持久力がないとか、瞬発力がないとか、身体が小さいとか、どこか欠けているものなんだけど、あの人は、なんに関してもずば抜けてたからね」(川田)
「やってて、嫌になっちゃうような人なんだよね。攻めてても、平気な顔して立ってきたりするから『効いてんのかよ!?』って、攻めてて嫌になっちゃう。技としては、バックドロップは身長があるし、身体が柔らかくてけっこう反るから効くしね。やっぱり、あの人は常人ではなかったよ」(田上)