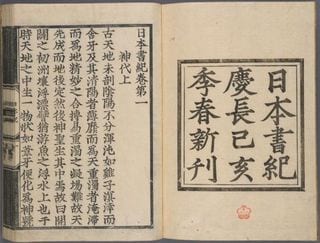Photo by Patrick Hendry on Unsplash
Photo by Patrick Hendry on Unsplash
(文:吉村 博光)
今年度の開高健ノンフィクション賞を受賞した傑作だ。京都大学大学院で「文化人類学におけるセクシュアリティ研究」に取り組む女性が、単身ドイツに渡り、複数の動物性愛者(ズー)の家を泊まり歩いて丹念に取材している。最初私は「動物性愛」ときいて腰が引けたが、興味が打ち勝って本書を開いた。すると、こんな書き出しが待っていた。
“私には愛がわからない。
ひと口に愛といっても、いろいろなかたちがあるだろう。”
この書き出しに続いて、長年受けてきた性暴力についての著者の自分語りが始まる。それは、動物性愛研究の動機でもあり、また、著者がズーの本質に迫ることができた理由でもある。本書には欠かせない告白だ。このプロローグを読めば、異種間の性に対する興味本位の本ではないことがわかり、私は思わず引きこまれてしまった。
獣姦と動物性愛は似て非なるもの
異種間の性といっても、獣姦と動物性愛が似て非なるものであることを、最初に断っておかなければならない。ときに暴力的な行為も含む獣姦との違いを認識したうえで、著者はドイツに渡っている。でなければ、携帯もつながらない田舎町の独身男性宅に何泊もするのは、リスクが高すぎるだろう。獣姦と動物性愛の違いについて、本書から引用する。
“「獣姦」と「bestiality」という単語で検索を続ける。おぞましい動画や画像を目にして、気持ちが萎えた。私にはこんなことを研究できないと思った。しかし、そのうち、私は「zoophilia」という言葉を知った。「動物性愛」のことだ。
動物性愛とは、人間が動物に愛着を持ち、ときに性的な欲望を抱える性愛のあり方を指す。~本書「プロローグ」より”
著者は、インターネットを通じてZETA(ゼータ)という動物性愛者の団体に連絡をとり、その4カ月後、はじめてドイツの地に降り立った。そこで待っていたのは、ミヒャエルという名の大男だった。車の後部座席には、キャシーという犬(妻)が乗っている。