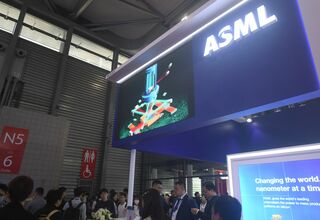では、前記した、保守系の恩恵を受けながら進歩系の改革を熱烈に支持する市民はいかに捉えるべきであろうか。こうした傾向は日本でも見たことがある。経営コンサルタントとして多くの組織改革を促してきた経験からすると、日本の大企業の経営陣から次の考えが透けて見える。「企業の競争力アップのため改革は大賛成だ」。ここまでは建前だ。次の本音を言う人はたまにしかいない。「だけど私がこの仕事から転出した後にしてほしい」。一種の抵抗勢力である。現行の恩恵を受けながら、スタンスとしては改革を支持する。国籍を問わずこのタイプを「超利己主義」と私は呼ぶ。これが三つ目だ。彼らは、現在の体制から一定の恩恵を受けていても、その権力構造を破壊するためなら手段を択ばない。そしてそのことを矛盾とも考えない。超格差社会が生んだ、現状打破を願う大衆とも言える。
実は、この超利己主義の層をいかにうまく掴むかがそれこそ政治ゲームプレーヤーの知恵比べということになる。彼らの支持を得られれば、世論の大勢を掴むことが出来るし、改革も進めやすいからだ。ただ問題は、これが果して民主主義を良い方向に導くのかどうか、だ。弱者である彼らの声を掬い上げることは、必然的に社会主義の考えに近づいていくからだ。実際、韓国はもちろん、アメリカでも社会主義的思想が市民の共感を獲得しつつある。
社会主義は20世紀に死ななかったのか
次に、曺氏の「民主主義と社会主義は両立できる」とした発言について考えてみたい。
日本の論客の中には、韓国はアメリカから離れ、中国に近寄っているという流れを主張する人がいる。文在寅氏が優先課題として掲げている北朝鮮融和政策と関連して、こうした傾向があることは否定しない。しかし、もう少し深く分析する必要があるのではないか。
ベルリンの壁崩壊後、アメリカのブレジンスキー元安全保障アドバイザーが『大いなる失敗』(The Grand Failure)という本を書き、20世紀の社会主義は大規模な、そして弊害の多かった実験であったが、失敗に終わったと主張した。ところが最近、変形した社会主義が再び注目を浴びるようになってきている。これは紛れも無く極度に開いた格差のためであろう。
こうした格差認識を決定付けた歴史的転換点がアメリカと韓国の両国にある。アメリカの場合は2008年のリーマン・ショックだ。ウォール・ストリート(金融エリート)という「1%」が弱者の「99%」を食い物にした、と人々はウォール街を占領しデモした。ちなみに、この年中国では北京オリンピックが開かれ、国民は自信を高揚させたと同時に、リーマンの悪影響を目の当たりにし、アメリカ流資本主義の限界を意識するようになった。
韓国の場合は2016年の朴槿恵(パク・クネ)前大統領と親友崔順実(チェ・スンシル)による不正発覚である。それ以前のセウォル号沈没事件の際、高校生など乗客(弱者)の救助を朴氏は優先しなかった。それとその後親友とされる崔氏の蓄財に政権の一部を導員し、企業まで巻き込んだこととの間のコントラストが市民を極度に怒らせ、朴氏は弾劾された。これにより左派政権が誕生したのである。
最近、欧米のメディアでは、アメリカの社会主義化に警鐘を鳴らす報道が目を引く。アメリカの民主党は極左とも言えるバーニー・サンダース上院議員、エリザベス・ウォーレン上院議員と、中道左派でオバマ政策を継承しようとしているバイデン元副大統領との間の論戦が注目を集めているが、アメリカ企業や富裕層は極左勢力の台頭に戦々恐々としている。「金持ちから奪い、貧困層に与える」(Take from the rich and give to the poor)という表現がアメリカにあるが、まさにそれを教育や福祉政策を通して実行しようとしている。
サンダース氏もこうした中、自身をどう位置付けるか模索しているようだ。北欧の「社会主義」はうまくいっていると言ってみたり、中国は莫大な数の人々を貧困から救い出したと言ったと思えば、中国の国家主導型社会構造や経済システムには警戒心を示してみたりもする。