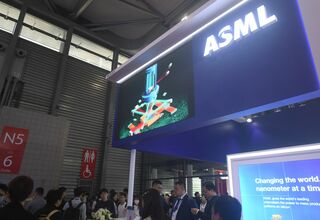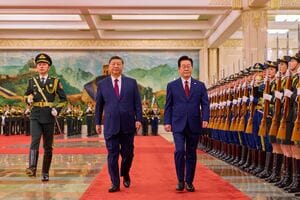魚群探知機は、開発当初、どれだけの市場規模が見込めるのか、いっさい分からなかったらしい。そりゃそうだ。そんな機械、過去になかったのだから。腕のよい漁師は、魚群を見誤ってばかりの開発陣を笑い、「機械に頼ろうとするからうまくいかないんだ」と揶揄していたという。
ところが、魚群探知機の開発に協力していた漁師が、村一番の漁獲高を連発で上げるようになるとコロリと態度が変わり、こぞって買い求めたという。いまや漁船で、小さなものを除けば、魚群探知機を備えていないものはないだろう。
大型コンピュータを凌駕したパソコン
新規事業は、それまでにない画期的なものであればあるほど、市場予測を立てることができない。そんなことは、ハーバード・ビジネススクールの教科書にもなっている「イノベーションのジレンマ」にちゃんと書いている。業界地図を根底から書き直してしまう破壊的イノベーションは、最初の姿はショボく、既存技術より劣っているように見える。けれど、破壊的イノベーションはたいがい、「価値規準の書き換え」を伴っている。だから、どれだけ既存の技術が優れていようと、太刀打ちできなくなる。
コンピュータがその好例だろう。私が高校生くらいまでは、コンピュータと言えば大型コンピュータが花形だった。私が中学生になる前にパソコンなるものが現れたが、能力は大変低かった。たとえば我が家にあったPC-6001という機種の主記憶は、増設して32キロバイトだった。どのくらいのサイズかというと、今なら、少し長文のテキストファイル2つ分くらい。そのくらいに小さいものだったから、できることは限られていた。
当時、国鉄(のちのJR)や電電公社(のちのNTT)には、大型コンピュータが据え置かれ、それを扱えるオペレーターは、重要な専門職で、大型コンピュータを扱えるよう訓練する専門学校もあったほどだ。そんな時代に、まさかパソコンが大型コンピュータをはるかにしのぎ、市場を席巻するようになるとは、多くの人は考えていなかった。
大型コンピュータはなぜ伸び悩み、パソコンの市場はどうして巨大化したのだろうか? 「価値規準の書き換え」が起きたからだ。大型コンピュータは、スピードも記憶容量も、パソコンとは比べようもないほど大きかった。スピードや記憶容量という「価値規準」でいえば、パソコンは勝負にならなかった。
ところがパソコンには、大型コンピュータが逆立ちしても真似できない価値を提供できた。「誰もが手に入れられる価格で売られていて、誰でもいじれる」だ。大型コンピュータは高価なだけに、専門的な訓練を受けた人間にしか扱うことが許されず、素人は触ることもできなかった。