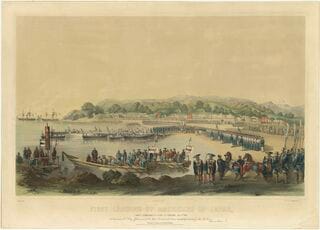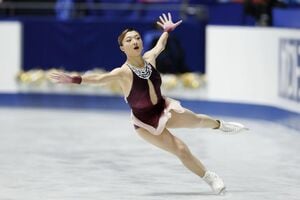勉強でエアコンをつけなかった主将
「背負ったふりして『被災した方たちに勇気と希望、感動を与えます』って、マスコミのみなさんに偉そうに言うほど浅はかな考えはないなって思っていたから。口先だけなら誰だって、いくらだって言える。みなさんが聖光学院に求めるのは言葉じゃなくて野球だから。本当に震災を背負う気があるんだったら、必ず行動に出る。顔つき、行動、試合中のプレー。そういうところで感じ取ってもらわないと意味がない。だから、『それができなかったら甲子園には行くな!』って、ミーティングではしばらく言っていた」
OB、現役世代問わず、斎藤の言葉が選手に響くのは、ひざを突き合わせた日頃の指導であり、時に彼らを「長い」と辟易させようと何時間でも話し続けられるほど、情熱を傾け、エネルギーを放出しているからだ。
2011年の世代では、エースの歳内宏明が象徴的な斎藤の体現者だった。
斎藤に「氷のような冷たい男」と評されながら、指揮官の言葉と指導によって2年生の夏に才能が開花。甲子園ベスト8の原動力となった歳内は、震災当初、主将を務めていた。「プロ注目の投手」として脚光を浴びていたこともあって、連日のように取材対応を強いられたが、「ひたむきにやるだけです」と多くを語らず、その姿は自らの生き様を見てくださいと言わんばかりだった。
歳内が当時の自分を振り返る。
「高校生が『震災にあった人たちの想いを背負う』とか、そんなおこがましいこと言えないですし、自分でも『それは違うんじゃないか』と思っていたんで。実際、部員で被災した人はいましたし、震災を考えること自体はいいことなんですけど、試合でそれを持ち出すのはズルいと思っていたんで。『震災を背負ったから勝てたんか?』といったら、それはまた違う話ですからね」
歳内の意志は、チームの共通認識でもあった。こんな逸話がある。6月にエースから主将を受け継いだ小沢宏明は、試験勉強をする学校内の会議室や寮では、斎藤が許可してもエアコンをつけなかった。それは、「体育館で避難生活を続けている被災者たちは、熱さに耐えながら生活しているから」という、小沢なりに導き出した答えだった。
このような行動に移すことによって、小沢は「背負うということ」に限りなく近づきたかった、と語る。
「聖光学院って、監督さんや先輩方の素晴らしい歴史があるのは間違いないんですけど、現役の選手ってそれを真似していた部分が多々あったと思うんです。震災があったからこそ『口だけじゃダメだろ』と。実際の行動に伴っていなければ何を話しても意味がないですからね」
歳内の振る舞い。小沢の行動。人が見ていようとそうでなかろうと、チームは紛れもなく震災を背負おうとしていたのだ。
無論、そのことは斎藤も感じ取っていた。