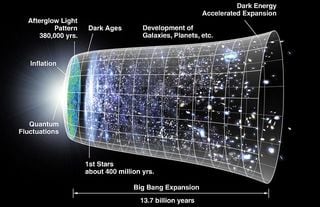ロシア語もわからず、生まれてこのかた雪を見たことは10回もあるかどうかというレベルであるにもかかわらず、著者は冬のロシアに降り立つ。そしてロシアの友人たちの力を借りて、ディアトロフ峠へと向かうのだ。
本書は、1959年のディアトロフ・グループの旅の模様と、2012年現在の著者の探索行が交互に語られる構成になっている。著者の語り口は巧みで、読む者を飽きさせない。
軍事機密に触れて殺された?
そもそも旅の出発点であるエカテリンブルクからして物語に富んでいる。ロマノフ王朝にかわってボルシェビキが権力を握った時、皇帝ニコライ一家はこの街の館に監禁されていた。皇帝夫妻と5人の子供たちは、館の地下で家族写真を撮るという口実で一列に並ばされたところを銃殺された。亡骸は郊外の沼地に捨てられ、ソ連崩壊後に引き上げられるまで、泥炭の中に埋もれたままだった(一家は2000年にロシア正教会によって列聖されている)。ちなみに一家が惨殺された時、幼い皇女アナスタシアだけは銃殺をまぬがれ、国外逃亡して名前を変えて生き延びたという伝説は、ロシアの陰謀論者の間では定番である。
ソヴィエト共産党支配の冷戦下では、この地に悪名高い強制労働収容所が建設され、多くの政治犯が収容され拷問を受けた。ディアトロフたちが生きていたのはそういう時代だったのだ。だからこそ軍事機密に触れて殺されたといった陰謀説が信憑性をもって語られる。陰謀論が流布する背景には、当時の体制に対する人々の根強い不信感があるのだ。
本書には一行が撮影した写真が数多く掲載されている。彼らは旅の間に88枚の写真を撮影していた。雪上で無邪気にふざけたり、笑顔でハグしあったりする写真は見ていて辛いものがある。1959年2月1日、最後の日に撮影された1枚は、キャンプ地へと向かう一行を後方から撮影したものだ。先頭は吹雪にかすみ、まるで闇の中に溶け込んでいくかのように見える。なんとも不穏な写真だ。
この日の日没は4時58分。テントを設営した一行は夜9時にテントに入った。そしてその後、生涯最悪の夜が彼らを待ち受けていたのだ。