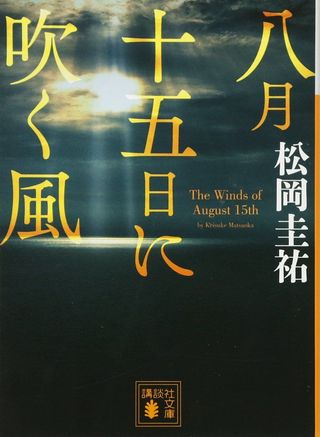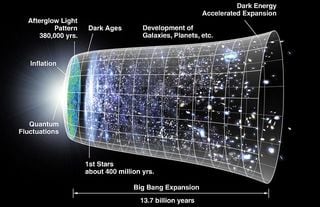(文:吉村 博光)
意表を突かれた。企画も内容も構成も、見事という他ない本だ。毎年、終戦の日にむけて様々な本が出版されるが、とりわけ異彩を放つ本である。本書を手にしてはじめて私は、「開戦を人々がどう受け止めたのか」という個々の情報が、ごっそり抜けおちていたことに気づいた。
“ものすごく解放感がありました。パーッと天地が開けたほどの解放感でした。
(本書11頁、吉本隆明、原典:三交社『吉本隆明が語る戦後55年・5』)”
“僕の命も捧げねばならぬ。一歩たりとも、敵をわが国土に入れてはならぬ。
(本書45頁、坂口安吾、原典:筑摩書房「真珠」『坂口安吾全集03』)”
本書は、太平洋戦争勃発時の知識人・著名人の反応を日記や回想録から抜き出した、アンソロジーである。さぞかし重苦しい空気なのかと思いきや、むしろその逆だった。戦争を歓迎する言葉が多いのである。知識人にして、そうなのだ。「一般人は?」と考えずにはいられなかった。
その問いの答えが、本書の最後にある。何とも心にくい演出だ。太宰治の短編小説『十二月八日』が収録されているのである。この小説は次のような書き出しではじまっている。「きょうの日記は特別に、ていねいに書いて置きましょう。昭和十六年の十二月八日には日本のまずしい家庭の主婦は、どんな一日を送ったか、ちょっと書いて置きましょう」
名文家の筆を借りて、当時の一般的な受け止め方を浮かび上がらせているのだ。絶賛ついでに言っておくが、そこに至るまでの構成も、じつに秀逸である。本書はまず、開戦を告げる午前7時の臨時ニュースから始まる。その後、吉本隆明、岡本太郎らの言葉が並ぶ。そして、午前12時の東條英機首相演説。