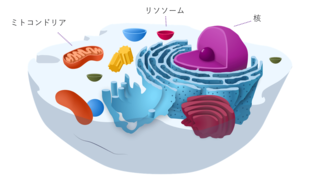〔AFPBB News〕ノーベル医学生理学賞の受賞決定を受け、都内で開かれた記者会見に臨む、東京工業大学栄誉教授・大隅良典氏(2016年10月3日撮影)。(c)AFP/Toru YAMANAKA
大隅良典さんのノーベル生理学・医学賞単独受賞は、嬉しいニュースだ。10日の授賞式では、基礎研究を心から愛する大隅さんが、世界の若い研究者に熱いメッセージを送られるに違いない。
私は東京大学理学部植物学教室で大隅博士と一緒に助手・講師をつとめ、その後、駒場キャンパスで一緒に助教授を務めたので、大隅さんの人となりをよく存じ上げている。
またその背景にあった植物学教室や駒場の、独創的な研究を大切にする文化を共有している。この経験にもとづいて、大隅さんがなぜ独創的なオートファジー研究を開拓できたか、そして“役に立たない研究”がなぜ役に立つかについて考えてみたい。
「面倒見の良い、隣のおじさん」
大隅さんのノーベル賞受賞の知らせを受けた私は、正直なところ「えっ、あの大隅さんが?」という驚きを隠せなかった。
大隅さんのオートファジー研究のすばらしさは知っていたし、朝日賞、京都賞などの数々の賞を受賞され、すでにノーベル賞の有力候補でもあったので、理屈では当然の受賞と理解できる。だが、「ノーベル賞受賞者」というイメージと大隅さんの人となりとが、どうにも合致しないのだ。
その後、基礎生物学研究所の毛利秀雄元所長による「隣のおじさん」という表現に思わず膝をうった。
「隣のおじさん-大隅良典君(ノーベル生理学・医学賞の受賞を祝して)」
<大隅君と接したことのある人達はお分かりのように、彼はおおらかでおだやかな性格であり、研究室には世界最先端のことをやっているといったピリピリした雰囲気はまったくありませんでした>
と毛利さんが書かれているとおり、大隅さんは「攻撃的」「権威的」などの言葉とは正反対にある、とてもおだやかな方だ。大隅さんは研究を愛されていて、研究に割く時間をとても大切にされているが、一方では教育熱心でもある。また助手時代から大学の研究環境を良くするための活動にも時間を割かれていた。一言でいえば、面倒見の良い人だ。
私は1983年1月に東大理学部植物学教室助手に採用されて大隅さんの同僚になったが、大隅さんと親しくなれたのは職員組合のおかげである。