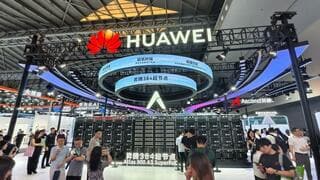CESでスピーチするNVIDIAのジェンスン・フアンCEO(1月5日、写真:AP/アフロ)
CESでスピーチするNVIDIAのジェンスン・フアンCEO(1月5日、写真:AP/アフロ)
2026年1月初旬、米ラスベガスでテクノロジー見本市「CES」が開催されたが、この会場で米エヌビディア(NVIDIA)が示した一連の施策は、同社の新たな野心を鮮明にするものだった。
「チャットボットの背後にある計算資源」という従来の役割を超え、物理社会のインフラをも掌握しようとする動きだ。
発表から3週間が経過した今、市場の関心は2つの話題に集中している。
次世代半導体プラットフォーム「Rubin(ルービン)」の量産開始と、自動運転タクシー(ロボタクシー)事業への参入だ。
これらが同社の掲げる「フィジカルAI」戦略において、どのような役割を果たしていくのか。その実効性に大きな関心が寄せられている。
ロボタクシー参入と「アルパマヨ」の役割
エヌビディアは、早ければ2027年にも提携企業と共同でロボタクシーサービスの試験運用を開始する計画だ。このサービスでは、特定の条件下で完全無人走行が可能な「レベル4」の技術を採用する。
同社はこれまで車載用チップ「DRIVE」シリーズの提供に徹してきた。今回、自らサービス運営の領域にまで踏み込む姿勢を見せたことは、業界に大きな衝撃を与えている。
2025年は、米グーグル傘下の米ウェイモ(Waymo)による商用化の成功や、米テスラの「Robotaxi」アプリの始動が相次いだ。自動運転が日常の選択肢となった年といえる。
エヌビディアはこの流れに対し、部品供給にとどまらない戦略で挑む。開発基盤そのものをオープン化した「Alpamayo(アルパマヨ)」を投入し、先行する競合各社に対抗する構えだ。
アルパマヨは、学習能力のみならず、推論能力をも強化した基盤である。特筆すべきは、モデルにとどまらず学習データまでも公開する方針を示した点だ。
自動運転では事故時の法的責任が厳しく問われる。
エンジニアが判断プロセスを検証できる「ペーパートレイル(証跡)」の確保は、極めて現実的な解決策といえる。
これは2024年制定の英国「自動運転車両法」に見られるような、責任の明確化を求める国際的な潮流を意識した動きだ。