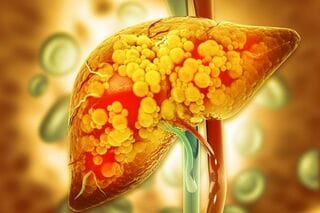ダボス会議にも登場したTikTokのロゴ(1月21日、写真:REX/アフロ)
ダボス会議にも登場したTikTokのロゴ(1月21日、写真:REX/アフロ)
2026年に入り、世界のテクノロジー市場は「地政学的な分断」と「デジタル経済の不可逆性」が交錯する特殊な局面に立たされている。
中国発の動画共有アプリTikTok(ティックトック)の米国事業移管が先月下旬に正式に決定し、数年に及ぶ膠着状態に終止符が打たれた。
これは一企業の存続問題を超えたもので、米中技術覇権争いの新たなルール形成を示唆している。
「ガバナンスと技術」を分離した異例の決着
先月の合意に基づき、TikTokの米国事業は米オラクルや米投資ファンドのシルバーレイクなどが出資する新法人へと移管された。
特筆すべきは、その資本構成とガバナンスの特殊性だ。
親会社である字節跳動(バイトダンス)の出資比率は20%未満に抑えられた一方で、サービスの心臓部であるレコメンデーション(推奨)アルゴリズムの所有権は依然として中国側が保持する。
この枠組みは、運営の実務やデータ管理を米国側が担い、技術の核心を中国側がライセンス供与するという「フランチャイズ型」運営モデルといえる。
米政府は国家安全保障上のリスクを「技術的な監査」によって封じ込める道を選び、中国政府は核心技術の流出を拒みつつ、巨大な市場価値を守り抜いた格好だ。
「アテンション・エコノミー」を購買行動へ直結させる適応力
今回の事案で浮き彫りになったのは、中国発のプラットフォームが持つ圧倒的な適応力だ。
米経済ニュース局CNBCの分析によれば、TikTokは昨年、政治的な逆風に晒されながらも、米国内のユーザー数を2億人にまで伸ばした。
これは米人口の約6割に相当する規模であり、もはや禁止措置を強行すれば社会的な混乱が避けられないレベルにまで浸透していることを示している。
こうした成功の背景には、高度に洗練された「アテンション・エコノミー(関心経済)」の活用がある。
情報過多の社会において希少な資源となった人々の「関心・注目」を、中毒性の高いアルゴリズムで奪い、それを広告収益や購買行動へと変換する仕組みだ。
さらに、中国発EC大手の「Temu(テム)」や「SHEIN(シーイン)」は、この「関心の占有」を即座に実際の購買行動へと結びつける導線を構築し、従来のマーケティング手法を塗り替えた。
シンガポール経営大学(SMU)のリアン・チェン教授が指摘するように、これら中国発のアプリは単なる「政策の隙間を突く存在」から、需要と供給を動的に制御する「適応型エコシステム」へと変貌を遂げている。
トランプ米政権による関税措置や、少額輸入免税制度「デミニミス・ルール」の撤廃といった政策的な障壁に対し、これらの企業は供給網の多角化や物流コストの吸収、さらにはサプライヤーとの価格交渉によって迅速に対応し、消費者のネット滞在時間とクリック数を経済価値に変え続けている。