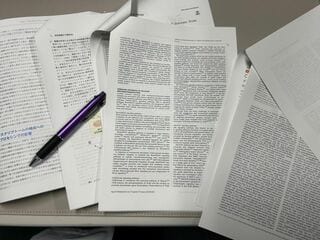米マサチューセッツ州にあるハーバード大学(写真:ロイター/アフロ)
米マサチューセッツ州にあるハーバード大学(写真:ロイター/アフロ)
(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)
科研費申請がひと段落し、研究者にとっては秋の学会シーズンが始まろうとしている。日本国内の学会であっても、今や英語でのコミュニケーションは当たり前。バイオ系の学会は特に海外からの来訪研究者も多く、会場では、海外のトップ研究者との質疑も活発だ。
かつて日本の研究者にとって研究留学は、キャリア形成における王道のステップだった。ただ、最近では、日本からの留学が減ったと言われることがある。この点については、オンライン会議や国際共同研究が普及し、世界の距離は縮まったように思え、情報の交換という意味では異質の世界に突入しているのだろうと考えている。
ただ、私自身がカナダのトロントと米国マサチューセッツ州ボストンという、海外の2つの地域の研究室に実際に所属した経験から感じることとして、現地の空気を吸いながら生活そのものを体験する意味は今もなお大きいということだ。
前回のコラムでは「研究の国際性」について触れたが、その延長線上で欠かせないテーマが「研究留学」だ。今回は、筆者自身の経験も交えつつ、研究留学の意義について考える。
留学は通過儀礼、そして「人生の夏休み」?
研究者のキャリアは、独自の研究テーマをどう育てるかにかかっている。そのため博士課程からポスドク時代にかけて、多くの研究者は複数の研究室を渡り歩き、異なる技術や視点を身につける。これらの経験がやがてオリジナルな研究の芽となり、独立への道を切り開く。
その過程で海外の研究室に所属することは、一種の「通過儀礼」といえる。国際的な舞台に立ち、自分の研究がどう評価されるのかを直接体感できるからだ。
筆者もハーバード大学医学大学院に留学していた際、のちにノーベル賞を受賞する研究者に発表内容を徹底的に指導されたことがある。がん患者の生存曲線のデータの説明の仕方が非常にまずかったのだ。正直「こてんぱんにされた」と言っていい経験だったが、今ではその意味もよく分かり、その指導は大きな糧となっている。