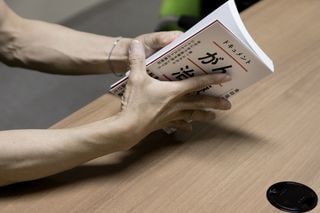がん細胞のミトコンドリアが免疫細胞へと取り込まれ、それによって免疫細胞の機能が抑制され、がん細胞が免疫からの攻撃を逃れて増殖を続けるというメカニズムが明らかになっている(写真:Kateryna Kon/shutterstock)
がん細胞のミトコンドリアが免疫細胞へと取り込まれ、それによって免疫細胞の機能が抑制され、がん細胞が免疫からの攻撃を逃れて増殖を続けるというメカニズムが明らかになっている(写真:Kateryna Kon/shutterstock)
(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)
6月を迎えると、大学や研究機関に所属する研究者にとっては、毎年恒例の「学会シーズン」が本格的に始まる。筆者は、がんの基礎研究に長年従事しており、日々、がん細胞の性質やその周辺環境、分子レベルでのメカニズムの解明に取り組んでいる。
研究活動を進めるうえで、最新の知見を収集し、他の研究者と議論を深める場として、学会への参加は欠かせない重要な機会だ。
「メタボローム解析」が拓く知られざる世界
筆者が毎年欠かさず参加している研究会に「がんと代謝研究会」がある。研究会は、参加者数がおよそ100人から200人程度の中規模な集まりだが、その構成や運営方針、雰囲気において他の学会とは一線を画しており、極めてユニークかつ魅力的だ。
代謝とは、簡単に言えば、生命活動を行う、さまざまな処理のことだ。エネルギーを作るのも代謝。息をして酸素を使うのも代謝。排泄物を出すのも代謝だ。
この研究会は、「がん」や「細胞内」の代謝を専門とする研究者を中心として構成されているが、参加者の研究分野は必ずしも限定されておらず、薬理学、生化学、免疫学、あるいは技術開発に携わる研究者など、広範な領域の専門家が集う。
「代謝」と一言で表現しても、その研究領域は非常に広い。
例えば、細胞のエネルギー獲得に関わる糖代謝、DNAやRNAの材料となる核酸代謝、タンパク質の構成要素であるアミノ酸代謝など、個々の代謝物質に焦点を当てた研究が存在する。
またそれにとどまらず、代謝の視点から「運動」「冬眠」「老化」など、個体レベルの生理機能やライフイベントに関連する形質を解析する研究も進められている。
一見すると、それぞれの研究テーマはバラバラで、統一性に欠けるように思えるかもしれない。ただ、これら多様な研究に共通して用いられている手法が存在する。それが「メタボローム解析」だ。
メタボローム解析とは、細胞や組織内に存在する多種多様な代謝物質を網羅的かつ定量的に測定し、その変動を解析する技術で、代謝研究の基盤となっている。これにより、特定の代謝経路の活性化や抑制、または代謝状態の全体像を捉えることが可能となるため、がんをはじめとする多くの疾患研究において欠かせない手法となっている。