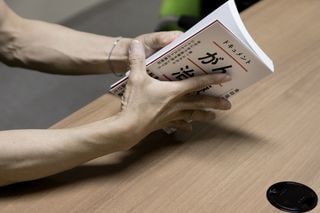「Warburg(ワールブルグ)効果」とミトコンドリアの役割
がんにおける代謝研究の出発点としてよく知られているのが、Otto Warburg (オット・ワールブルグ)博士によって発見された「Warburg効果」である。
残り5045文字
がんにおける代謝研究の出発点としてよく知られているのが、Otto Warburg (オット・ワールブルグ)博士によって発見された「Warburg効果」である。
残り5045文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら