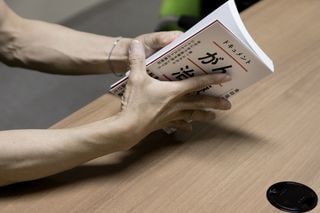乳がんは若い頃に種がまかれ、長い時間をかけて育っていくという(写真:elutas/イメージマート)
乳がんは若い頃に種がまかれ、長い時間をかけて育っていくという(写真:elutas/イメージマート)
(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)
筆者が、がん研究の道を歩み始めたのは北海道大学だ。その後、東京大学での胃がん研究を経て、乳がん研究へと研究分野を変更し、カナダ・トロントのPrincess Margaret Cancer Centre、さらにアメリカ・ボストンのBeth Israel Deaconess Medical Center/ハーバード大学医学部へ留学した。
そこで偶然にも、乳がん細胞が特定のアミノ酸を巧みに制御し、増殖しているという現象を発見し、日本でも名を聞いたことがある人も多いであろう世界的な学術誌『Nature』にその成果を発表することができた。帰国後は、日本国内で研究費の獲得や共同研究を通じて、がんの解明に挑み続けている。
もう20年近くがんの研究の最前線に立っているわけだが、今なお「がんとは何か?」という本質的な問いには、完全な答えが見えていない。がんという病は、我々が思っている以上に奥深く、そして複雑だと言える。
がんとは、いったい何か?
「がんは遺伝子の異常によって、細胞が際限なく増殖していく病気」とよく言われる。これ自体は正しいのだが、がんの正体はもっと複雑で、深く理解しようとすればするほど謎が増えていく。
また、がんは体内に新たに生まれる未知の生命体のような存在とも言える。このような視点からがんを捉えるのが、「腫瘍生物学」という学問分野だ。がん研究にとどまらず、生物そのもののシステムの理解にもつながる重要な視点である。
本稿では慶應先端研で講義している入門的な話を軸に、その難しさに触れる。