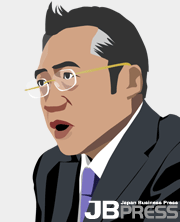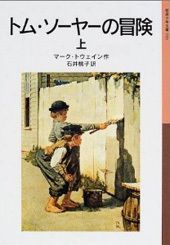報酬規制、人材流動化時代が到来
世界経済が同時不況に陥り、その引き金を引いた金融界への怒りは激しさを増す一方だ。4月2日、第2回G20金融サミットが開かれたロンドンでは、会合と銀行救済に反対する激しいデモが繰り広げられた。英在住の投資銀行家は「バンカーに見えないよう」ジーンズ姿で出勤し、大手紙ロンドン特派員は「トラブルに巻き込まれないよう」ノーネクタイで取材。関係者が身の危険を感じるほど、金融への風当たりは強まっている。
もはや報酬規制は避けて通れない。G20はロンドン会合で「金融システム強化に関する宣言」を打ち出し、金融機関の報酬体系に関する原則の導入を承認。各国の監督当局に対し、3つの柱の年内実施を促した。
- (1)金融機関の取締役会は報酬体系の設計、運用、評価を積極的に実施する。
- (2)賞与を含む報酬はリスクを反映し、リスクが生じる期間中に支払う。リスクが長期間を経て実現する場合は、支払いは短期に完了すべきではない。
- (3)金融機関は報酬について、株主を含む利害関係者が監視できるよう情報開示する。
「金融機関が短期業績に連動した報酬に突き動かされ、リスクを取り続けたことが今回の危機を招いた」(政府交渉筋)との反省から、この報酬原則は「社内や利害関係者の監視の下、投資リスクの結果が見えた後で報酬を支払う仕組み」(同)を求めている。
さらに、G20は各国当局に対して「健全性判断の一環として、金融機関の報酬政策を評価し、必要があれば所要自己資本の増加を含めて介入する」よう要請。金融庁幹部によると、この表現は「過度なリターンを確認できた場合、応分の資本を積むよう命じており、事実上の高額報酬の規制になる」という。
証券化商品市場が壊滅して報酬規制も強まる中、米欧金融界は「10年前のように必死にロケットサイエンティストを集める必要性はなく、集められる魅力も失う」(米銀幹部)。人材紹介会社の試算では、昨年初~今年3月末までの15カ月間で外資系金融の日本法人は15%の人員を減らした。米欧ではより多くの削減が進んでおり、再雇用の見通しは暗い。
しかし、コインに表と裏があるように、ある官庁エコノミストは次のように指摘する。「ロケットサイエンティストが金融工学を発展させたように、今では想像もつかない新技術が10年後の世界を変えているかもしれない。いつか、『2008年金融危機』に感謝する日が来るはず」「冷戦終結以来の人材流動化時代に入ることを意識して、将来の産業育成に向かうべきだ」
野村と三菱UFJ、報酬改革が難題に
給与格差、「リーマン組」と確執も〔AFPBB News〕
日本の金融界への影響はどうか。国内ではメガバンクや大手証券ですら、海外で問題化している高額報酬とは縁遠く、「G20の報酬規制は所詮、海の向こうの話」(邦銀企画担当)と冷めている。だからこそ、金融庁のある幹部は「邦銀は株主や社外からの監視を強めた上で、逆に成功報酬の要素を強めてもよい。野に放たれる逸材を採用するチャンスだ」と指摘する。
そういう観点から、この幹部はリーマンの欧州・アジア部門を買収した野村ホールディングスや、米モルガン・スタンレーに90億ドル出資した三菱UFJフィナンシャル・グループの動向に関心を示す。「腕利きバンカーや金融工学のプロフェッショナルを獲得すれば、世界に飛躍する機会にできるはずだ」と期待を膨らませている。
実際、両社は「巨大M&Aを機に報酬改革を進め、日米の強みを生かしたビジネスモデルを目指す」(野村幹部)という。しかし、「日本型の賃金体系がもたらす組織の安定」(同)を放棄するのは容易ではない。
今春、野村に入社した新卒者は約720人。関係者によると、このうち人数は定かではないが、「リーマン内定者」の基本給は「野村内定者」の3倍近い。このため社内では、「リーマン出身の高給取りを『L』と隠語で呼び、軋轢が生じている」(関係者)。野村は「外資に準じた年1度の賞与導入」「業績連動報酬の選択制」を推し進めるが、異文化融合には相当時間がかかりそうだ。
そして、三菱UFJは傘下証券とモルガン・スタンレー日本法人を2010年3月末までに統合させる計画を公表したものの、「『石橋を叩いても渡らない』三菱の風土で、米系の強みを生かせるのか」(関係者)と早くも疑問符が付けられている。報酬基準の構築が、難題として立ちはだかっている。