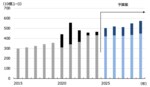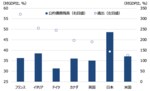財政拡張路線に舵を切ったドイツだが、労働力不足というボトルネックの下、本当に景気回復につながるのか?
【土田陽介のユーラシアモニター】前年比6%増となる拡張予算を組むメルツ政権、サボリ癖がついたドイツ人の動向が鍵
土田 陽介
三菱UFJリサーチ&コンサルティング・主任研究員
2025.6.30(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
レアアースの輸出制限でEV関税の撤廃を目論む中国に揺さぶられる欧州、簡単ではなかったEUの対中デリスキング