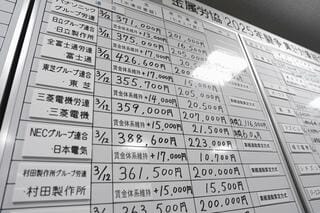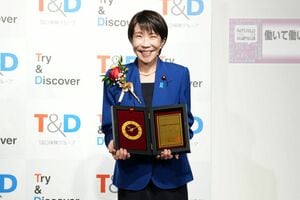月給が上がっても「年収」「生涯賃金」が下がるケースも
まず1つ目は、月給が高くなっても年収は低くなってしまうケースです。例えば、月給22万円で賞与が6カ月支給される場合。多くの会社は月給の大半を占める基本給をベー
残り3280文字
まず1つ目は、月給が高くなっても年収は低くなってしまうケースです。例えば、月給22万円で賞与が6カ月支給される場合。多くの会社は月給の大半を占める基本給をベー
残り3280文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら