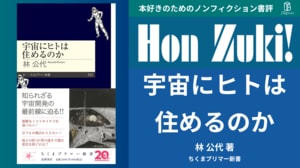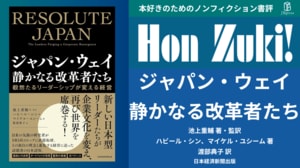圧倒的なソ連軍を翻弄した「名将」として評価される一方、ヒトラーの人種絶滅政策に唯々諾々として従う戦争犯罪人として同じだけの非難も受けたドイツの知将、エーリヒ・フォン・マンシュタイン
圧倒的なソ連軍を翻弄した「名将」として評価される一方、ヒトラーの人種絶滅政策に唯々諾々として従う戦争犯罪人として同じだけの非難も受けたドイツの知将、エーリヒ・フォン・マンシュタイン
1941年の6月22日に、独ソ戦は始まった。この独ソ戦をはじめ、第二次世界大戦当時のドイツ軍には、「天才作戦家」と呼ばれる知将が存在した。名は、エーリヒ・フォン・マンシュタイン。戦略・作戦・戦術という、戦争の三階層においては、上位次元の劣勢を下位からくつがえすことは難しい。数々の戦場で、そのほぼ不可能な課題をやってのけたマンシュタインとはどのような人物だったのか。現代史家の大木毅氏は、新著『天才作戦家マンシュタイン 「ドイツ国防軍最高の頭脳」――その限界』で、改めてマンシュタインの実像とその評価に迫った。
(*)本稿は『天才作戦家マンシュタイン 「ドイツ国防軍最高の頭脳」――その限界』(大木毅著、角川新書)の一部を抜粋・再編集したものです。
玄人筋に絶賛された知られざるドイツの名将
エーリヒ・フォン・マンシュタインは、北アフリカで連合軍を翻弄し、「砂漠の狐」の異名を取ったエルヴィン・ロンメル元帥や、ドイツ装甲部隊の育成に大きく貢献、自ら指揮したハインツ・グデーリアン上級大将に比べれば、知名度においては一歩劣るかもしれない。
しかしながら、ドイツの将軍たちや敵である連合軍の司令官など、いわば玄人筋は、参謀本部の保守本流ともいうべきエリートコースを歩み、多大な功績を残したマンシュタインに対し、高い評価を加えている。
事実、戦後すぐから1950年代にかけて、マンシュタインこそ1940年のフランス崩壊をもたらした作戦の天才であり、人格高潔で騎士道的な指揮官だったとする言説が流布されていった。
そのなかには、軍事のアマチュアであるヒトラーが東部戦線の作戦指揮に介入することを許さず、マンシュタインに自由にやらせていたら、対ソ戦は勝てた、少なくとも引き分けに持ち込むことができたというような主張も含まれていたのである。
しかしながら、かかる「完全無欠の軍人」であったという評価は、ロンメルの死後(周知のごとく、彼はヒトラー暗殺未遂事件に関与したとされ、1944年に服毒自殺させられている)旧部下や崇拝者が「砂漠の狐」について描きだした像、あるいはグデーリアンが自らの回想録で広めたイメージ同様に、つくられたものにすぎない。マンシュタインもまた、戦後すぐ、あるいは戦争中から、そうした「名将」の評判を得ることに腐心していたのだ。