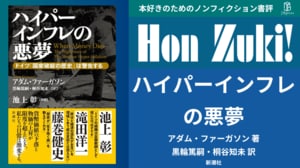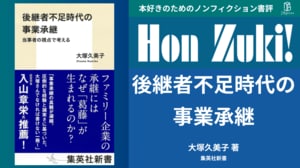つくられた「名将」の幻影
このマンシュタインの自己弁護・美化をはかろうとする姿勢は、すでにニュルンベルク国際軍事裁判(1945~1946年)のころからあきらかであったが、それがよりいっそう明確に打ち出されたのは、1955年に刊行された回想録『失われた勝利』であった。マンシュタインはそこで、おのれはかくあったと信じ、また、他者にもそう思わせたかった姿に合わせて、自画像を描きだした。
今日の眼でみれば、それは偽りを含んだものにすぎないのだけれども、当時はマンシュタインが第二次世界大戦で示した巨大な功績のオーラを受けていたから、たちまち広範な層の支持を得た。
しかも、その高評価はドイツにとどまらず、イギリスの高名な軍事史家・戦略思想家であるバジル・リデル゠ハートの肝いりで英訳版が刊行されてからは(1958年)、世界的に広まっていったのである。
日本もまた例外ではない。ドイツ語を解し、戦前戦中からマンシュタインの事績に注目してきた、本郷健や加登川幸太郎をはじめとする旧陸軍将校たちが、戦史研究家として、あるいは『失われた勝利』を邦訳出版し、あるいは彼の軍事的手腕を称賛する著作や雑誌記事を多数発表した。それによって、「名将」マンシュタイン像は、日本にも輸入されたものといえる。
さりながら、いかにマンシュタインが自らの戦功を強調し、彼のシンパが多大なる支持を与えたとしても、それだけでは、マンシュタインのセルフ・ポートレートが、第二次大戦史についての世界的共通認識の一部をなすというところまで行くのは難しかったはずだ。マンシュタイン「神話」が、かくもたやすく人口に膾炙するに至ったのは、冷戦という歴史的背景が大きく与っていると思われる。
 1943年3月、ヒトラーはウクライナのザポロジェにある南方軍集団の本部に到着した。写真は、現地の飛行場でヒトラーを出迎えるマンシュタイン(写真:Bundesarchiv / Bild 146-1995-041-23A / CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
1943年3月、ヒトラーはウクライナのザポロジェにある南方軍集団の本部に到着した。写真は、現地の飛行場でヒトラーを出迎えるマンシュタイン(写真:Bundesarchiv / Bild 146-1995-041-23A / CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)