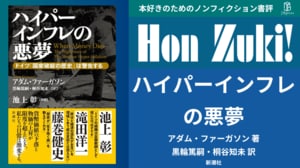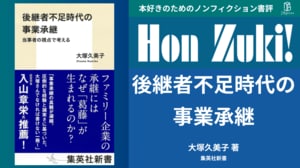伝説にお墨付きを与えた西側の現役高級将校たち
冷戦当時、とくに1970年代から1980年代にかけて、西欧諸国はヨーロッパ正面において、圧倒的な優越を誇るソ連軍、のちには、ワルシャワ条約機構軍と対峙していた。対するNATO、北大西洋条約機構の軍隊としては、核兵器を使用するという禁断の決定に踏み切るのでなければ、質的優位によって量に対抗するほかない。つまり、NATO軍は、独ソ戦後半のドイツ国防軍が置かれたのと同様の状況にあった。
かような立場にあるNATO軍の指揮官にとって、質の優位、作戦の妙を以てすれば、数に優るソ連軍をも撃破し得るというマンシュタインの主張と実績は、おおいに傾聴すべき議論であり、同時に救いでもあった。ゆえに、マンシュタインは西側のプロの軍人たちに称賛された。いわば、「名将マンシュタイン」の伝説は、当時の現役高級将校たちによって、お墨付きを与えられたのだ。
いずれにしても、マンシュタイン評価にあっては、こうしてまず「人格高潔な名将」というテーゼが成立した。そのテーゼは、東西対立という認識の枠組みのもと、1955年の『失われた勝利』刊行以来、三十余年にわたって守られてきたのである。
しかしながら、1989年以降の東欧共産圏諸国、さらにはソ連邦の崩壊を受けて、歴史の再検討が進むとともに、第二次世界大戦史への視角は大きく変わった。冷戦のあいだ、ドイツ国防軍は、ソ連共産主義と戦った「先達」として、ある種の「敬意」を受けてきた。
戦争犯罪、あるいはナチ犯罪に関しても、親衛隊とは異なり、戦争法規を守って、国民を防衛する戦争を遂行したとされていたのだ。いわゆる「清廉潔白な国防軍」という神話である。
冷戦後に評価が一変したマンシュタイン
ところが、冷戦という「戦時」が終わり、東側との対峙という大前提がくずれると、ドイツ国防軍を聖域としておく必要はなくなった。こうした事情を背景に、ドイツ国防軍とナチズムの侵略ならびに人種絶滅政策との関わりがクローズ・アップされ、実はその手も汚れていたではないかという糾弾が行われるようになってきたのである。
そうして歴史認識があらたまるとともに、輝かしいマンシュタイン像にも影が差しはじめる。マンシュタインのナチズムへの親和性、あるいは、その戦争犯罪への関与を指摘し、元帥の責任を問う論考が現れてきたのだ。その傾向は、21世紀に入ってから顕著となり、マンシュタインを批判する研究書や論文が多数出された。
それらのうち、代表的なものとして、イスラエルのマーセル・ステイン(ステインは1940年にフランス軍に従軍した経験を持つ在野研究者である)による『フォン・マンシュタイン元帥 双面神の頭』(初版2004年)ならびに、ドイツのオーリヴァ・フォン・ヴローヘムの『エーリヒ・フォン・マンシュタイン 絶滅戦争と歴史政策』(初版2006年)が挙げられる。
彼らは、「人格高潔な名将」テーゼと正面から対決した。マンシュタインは、ヒトラーの侵略や、ユダヤ人ほか、ナチが「劣等人種」とみなした人々の絶滅政策に異を唱えなかったばかりか、そうした非道な政策が実行されるのを止めようとしなかった、政治的・倫理的に問題のある軍人だと非難したのである。
とくにヴローヘムは、マンシュタイン指揮下の第11軍が独ソ戦のクリミア作戦中に行った戦争犯罪を詳細に調べ上げた。その結論は、マンシュタインにはそのような蛮行に対する責任があるというものだった。
名将の顔と、戦争犯罪人の顔と……
これらの研究が出版されてからというもの、歴史認識上のマンシュタインは、まさしく「双面神の頭」を持つことになった。双面の一つは圧倒的なソ連軍を翻弄した「名将」の顔、もう一つはヒトラーの人種絶滅政策に唯々諾々として従う戦争犯罪人の顔であることはいうまでもない。しかも、本書序章で叙述したように、マンシュタインは、知らぬ、記憶にないと、後者の顔を否定しつづけたのであった。
かくて、「人格高潔な名将」テーゼに対し、「責任逃れの戦争犯罪人」というアンチテーゼが提示されたのである。