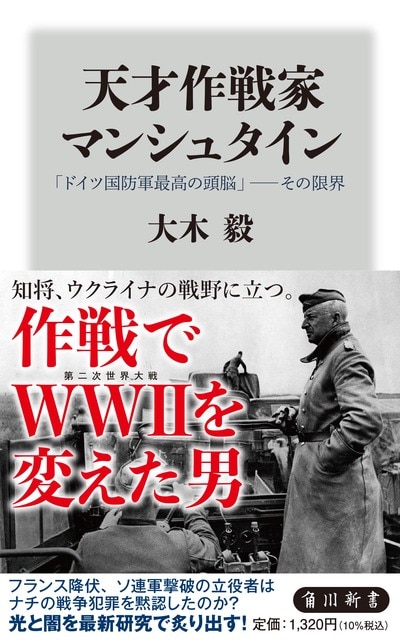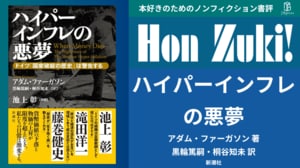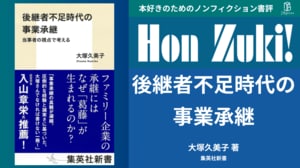「戦略的な限界を抱えた天才作戦家」
思考の枠組みである弁証法に関するごく一般的な理解では、ある主張(「正」)に対して、それを否定する異なる議論(「反」)が出され、この「生」と「反」の内容を保持しつつ、より高い次元で総合がなされ(「止揚」)、あらたな定立(「合」)がみちびかれる。弁証法が、対立する命題から新たな理解を得る思考法と呼ばれるゆえんだ。
歴史学、あるいは広く人文・社会科学においても、弁証法的な議論の結果、さらに包括的な解釈が得られることは珍しくない。マンシュタインの研究史についても、それは当てはまる。
戦後すぐから冷戦末期に至るまでの名将顕彰的なテーゼへの反動もあって、21世紀に入ってからのマンシュタイン研究では、「戦争犯罪人」のアンチテーゼにもとづくものが多数であった。いわば、マンシュタインの評価は、称賛と非難、テーゼとアンチテーゼの股裂き状態に置かれていたといっても過言ではあるまい。
英国軍人による新しいマンシュタイン評
しかし、2010年には、そうした両極端の議論を止揚し、マンシュタイン像の総合的な再構築を試みた大部の評伝が刊行された。マンゴウ・メルヴィンによる『ヒトラーの元帥 マンシュタイン』である。
メルヴィンは英国陸軍の軍人で、参謀本部陸戦監、国防省作戦能力監督部長、在独英軍給養司令官などを歴任した高級将校だった(最終階級は少将)。それが、在独英軍勤務時代に、ドイツ連邦国防軍の軍事思想と歴史に興味を持つようになり、マンシュタインを研究テーマとしたのであった。
このメルヴィンによる伝記で特徴的なのは、いわゆる「戦争の諸階層」、戦略(外交・同盟政策、国家資源の戦力化、戦争目的の設定等)、作戦(戦略の目標を実現するために、一定の時間的・空間的領域で行われる軍事行動を立案・実施する)、戦術(作戦の実施に際して生起する戦闘に勝つための方策策定と実行)の三次元からみて、マンシュタインはいかに評価されるべきかという問題意識を堅持しつつ、その生涯を論述していることであろう。イギリス軍改革に深く関与した軍人ならではの視点といえる。
やはり卓越していたマンシュタイン
こうした問題意識のもと、メルヴィンはマンシュタインの生涯における軍事的判断や決定を検討し、彼はやはり作戦次元において卓越した軍人だったとの結論を出した。
ただし、戦争犯罪への関与については、マンシュタインが「責任を負っていた地域で広範に行われていたソ連捕虜の虐待、いわんやユダヤ人の大量殺害について何も知らなかったなどということが本当にあり得たのだろうか」と問いかけた上で、しかし、「かかる根本的な疑問に対して確答できずにいる」と告白している(メルヴィン上巻所収「日本語版への序文」)。
メルヴィンは、専門家として旧ユーゴスラヴィアにおける戦争犯罪を裁いた国際法廷に証人出廷したことがある。その経験もあって、禁欲的な姿勢を選んだものか、いわゆる「推定無罪」の原則に従ったのである。そのため、『ヒトラーの元帥 マンシュタイン』の論述は、あまりにも軍事面に偏していて、ナチ犯罪・戦争犯罪との関わりについて、深く追及していないという批判が寄せられたりもしたけれど、それについては著者も覚悟の上だったのかもしれない。
いずれにしても、このメルヴィンによる評伝は、上のような批判があったとはいえ、国際的に高い評価を受け、今日では、マンシュタイン研究者がまず依るべきスタンダードになっているとみてよかろう。