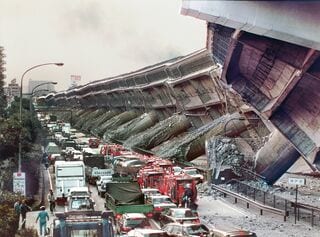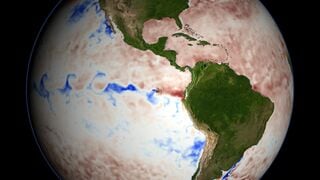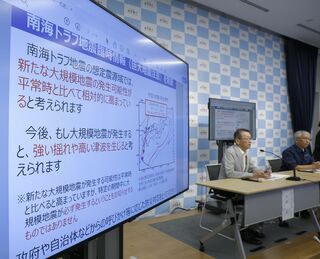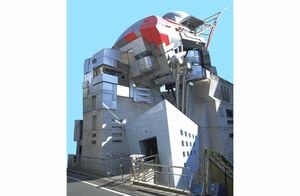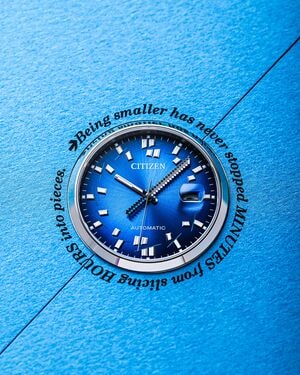林野火災の発生条件が揃っていた大船渡林野火災の規模
林野火災が発生し延焼する原因は、一般的には周知のとおり空気の乾燥と強い風にあります。事実、大規模な林野火災は冬〜春にかけて、太平洋側と瀬戸内地方で多く発生する
残り1872文字
林野火災が発生し延焼する原因は、一般的には周知のとおり空気の乾燥と強い風にあります。事実、大規模な林野火災は冬〜春にかけて、太平洋側と瀬戸内地方で多く発生する
残り1872文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら