【高額療養費】負担増いったん見送りされたが…医療費で生活圧迫されている国民の実態、石破首相は分かっているのか
2025.3.12(水)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴
【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには
小林 啓倫

【ミラノ・コルティナ五輪展望:アイスホッケー女子】 準々決勝通過なるか、「スマイルジャパン」に込められた思い
松原 孝臣
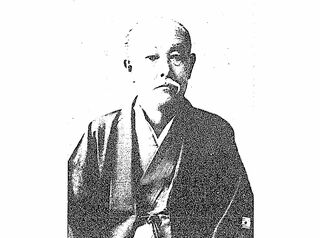
言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及
幕末維新史探訪2026(5)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語⑤
町田 明広

「がんの一つや二つあって当たり前だろう」それでもやはり見つけられたくはない
勢古 浩爾
明日の医療 バックナンバー

「病院に行っても断られる」時代がすぐそこに、インフレ直撃の医療現場が直面する“夜間スタッフ消滅”の危機
中山 俊

医療現場で具体的かつ劇的な成果を上げているAI、研究の「コパイロット」になる時代に人間に残される2つの役割
齊藤 康弘

来年開始の医学部定員削減で「地域医療崩壊」に現実味、この課題に医学部受験専門予備校「京都医塾」が取り組む理由
三重 綾子

【アルコールは発がん物質】アルコールの毒は一種類ではない、細胞の「傷つけ役」が体内で次々に増えていく怖さ
齊藤 康弘

【高額療養費制度見直し】「財源に限りが、だから困っている人だけ助ける」では救われない重病・難病患者が続出する
坂元 希美

身体がほとんど動かない重度障害の患者との意思疎通は可能か?微かな動きから読み取る人々と動かない身体が語ること
長野 光 | 西村 ユミ








