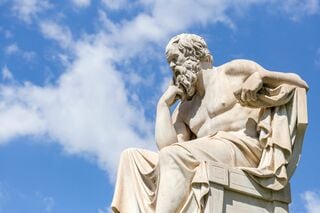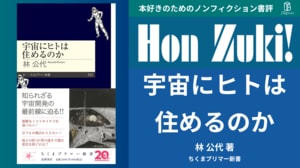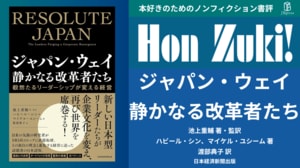旧ソ連の崩壊による冷戦終結後、世界はアメリカ一強体制になり、以降、アメリカは単独覇権の維持を目指してきたが、今その影響力は急速に低下してきている。
特に、経済構造の脆弱性と軍事的な負担の増大は深刻な状況にある。アメリカ経済は金融とテクノロジー分野への依存を強める一方で、製造業は長年にわたって衰退してきた。同時に、イラクやアフガニスタンなどとの過去の戦争による軍事コストの増大は、国家財政を大きく圧迫してきている。
こうした中で、ヴァンス副大統領の『ヒルビリー・エレジー』に見られるような労働者階級の没落や中間層の衰退が、経済格差や政治的分断を加速させており、これがトランプ現象やポピュリズムの台頭につながっているというのである。
これに対して、経済制裁を受けながらも社会の安定を維持しているのがロシアである。
歴史的に、対フランス、対ドイツとの戦争や度重なる経済危機を乗り越えてきたロシアの底力が、今回の戦争でもいかんなく発揮されているとトッドは言う。特に、人口動態的に安定しており、伝統的な家族構造も維持されていることがロシアの強みであり、単に軍事大国としてだけでなく、文化的・歴史的な独自性を持つ国家として、西洋とは異なる発展の道を歩んでいるというのである。
また、中国もアメリカの覇権に対抗しうる唯一の超大国として着実に成長を続けており、トッドは、今後、中国がアメリカとの競争において優位に立つ可能性を展望している。かつてのようにアメリカとヨーロッパが圧倒的な支配力を持つ時代は終わり、中国やロシア、更にはインドや他の新興国が台頭することで、世界は西洋中心から多極化へ向かうという。
他方で、「西洋の敗北」は必ずしも中国やロシアの勝利を意味する訳ではなく、宗教面、教育面、産業面、道徳面における西洋自身の崩壊プロセスの帰結であるとしている。そして、西洋がこうした変化を受け入れ、新しい国際秩序の中でどのように自らの立場を確立していくかが重要なのだと説いている。
「日本の保護がなければ書けなかった」とトッド氏
本書のもうひとつの論点が、アメリカやヨーロッパの西洋中心的な世界観と、そうした西洋的価値観の押し付けという問題である。
本書の冒頭で、トッドは「日本の読者へ」として、次のような前書きを寄せている。
「本書は、日本の保護がなければ書けなかっただろう。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、西ヨーロッパが受けた精神的ショックはあまりにも大きく、そこでは長い間、独立した思考は不可能になってしまった。ロシアとアメリカの間で始まったこの紛争について、たとえばフランスのような国にいながら歴史学者、そして人類学者として客観的に考えることは知的な意味で危険なこととなった。こうして私は、自国でおよそ8カ月間、沈黙を保たなければならなかった。」