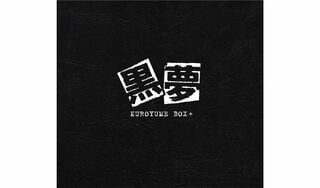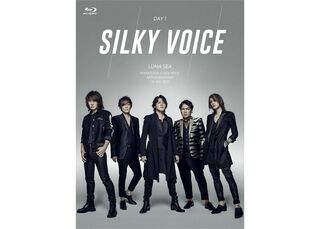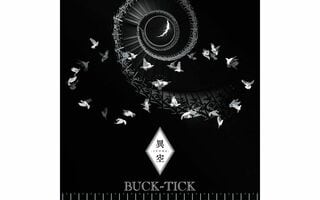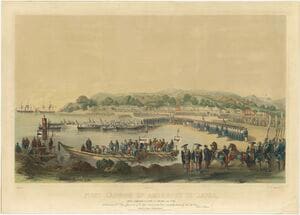ヴィジュアル系っぽいギタープレイとサウンドメイク
こうした布袋のギタープレイ、“キャッチーなイントロ”と“クリーントーンのカッティングプレイ”は日本独自のビートロックを象徴するギターサウンドの代名詞となった。
残り2758文字
こうした布袋のギタープレイ、“キャッチーなイントロ”と“クリーントーンのカッティングプレイ”は日本独自のビートロックを象徴するギターサウンドの代名詞となった。
残り2758文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら