事業が崖っぷちでも他人事、危機感なき社員のマインドを一発で変える方法
三枝匡氏が唱えるV字回復のセオリー「『強烈な反省論』を出発点に」
2023.5.2(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

EVトラック普及の鍵はDX、いすゞと三菱ふそうが設計した驚きのサポート内容
机上の空論ではなく、現場密着でつかんだ顧客ニーズを生かした独自の仕様書
井元 康一郎

「1秒チェックイン、1秒チェックアウト」にこだわったアパホテルDX化の強み
D2Cの「アパ直」を軸に宿泊者の利便性をとことん追求する仕組みとは?
河野 圭祐

竹中工務店が描く「デジタルプラットフォームでつながる建設業界の未来」
デジタルの力で2024年問題を解決、業界の魅力も向上させる
吉川 ゆこ
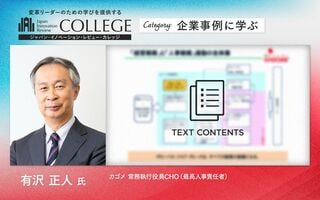
「カゴメは変わった」社員も驚く人事制度改革、目指す先は“生き方改革”
「人事制度は経営の意思・覚悟を示すメッセージ」トップ自ら変わることから始まる
有沢 正人

清水建設・山本金属製作所から学ぶ、「デジタルツイン」で会社はどう変わる?
シリーズ「なぜ、CXが進まない?ものづくりDXを阻む企業に巣くう根深い問題」(5)
八子 知礼
本日の新着

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②
町田 明広

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影
生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に
小久保 重信

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか
【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至
唐鎌 大輔

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く
【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか
菅原 淳一
経営を強くする バックナンバー

【2025年謝罪大賞】ワースト3位は「子ども向けキャンペーンに転売ヤーが殺到した」事件、そして1位はあの無理筋な…
増沢 隆太

“AIリストラ時代”の到来、真っ先に人員削減の対象になる「3パターン」と職場が見落としがちな最重要課題とは?
川上 敬太郎

チョコプラ謝罪動画の失敗が教えてくれる「謝罪時のよい手土産は?」の答え、丸刈り・土下座・和菓子より大事なこと
増沢 隆太

“タワマンの街”武蔵小杉から始まった川崎市の人口増、小田栄駅に続く「戦略的新駅」第2弾は出てくるのか?
小川 裕夫

「ハッピーセット」のポケカ転売騒動で大炎上したマクドナルド、学んでほしいタミヤのブランドマネジメント
増沢 隆太

日立の「白物家電」売却報道で危ぶまれる“日の丸家電”の存続、なぜ日本メーカーは急速に力を失ったのか
関 慎夫



