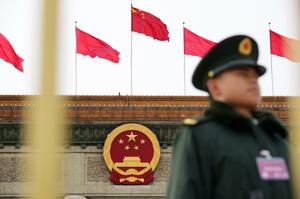豊かになった村、薄らぐ核燃料サイクルへの不安
大間から下北半島の付け根に位置する六ヶ所村に車を走らせた。
冷たい霧に包まれた道路の所々にブリザ―ド避けの遮蔽板、真冬の厳しさが想像される。
六ヶ所村もひと昔前は典型的な寒村だった。多くの村民が冬は出稼ぎに出、若者は仕事を求めて都会へと村を去った。
だが、初めて訪れた六ヶ所村にその頃の面影はなかった。ぐるりと村を取り囲む広い道路、造成中のニュータウン、立派な温泉スパ。村の住宅も殆んどが比較的新しく、余裕ある生活が窺える。
村が寒村からこのハイリッチな村へと変わるきっかけはそもそも、1969年に始まった国の「むつ小川原開発計画」だったが、その石油コンビナート計画は頓挫する。
まさに村を二分して何年にも及んだ論争の末に開発へと舵を切り、農地や漁業権を手放した村民に残された広大な空き地。そこに持ち上がったのが「核燃料サイクル施設」の立地話だった。1984年のことだ。他に選択肢もなく村は受け入れを決めた。怖いという意見は出たが、反対は少数だった。補償金も交付金も入る。地元で働ければ“出稼ぎ”に出なくても暮らしが成り立つ。
そうして90年代に入った村ではウラン濃縮工場、低レベル放射能廃棄物センター、高レベル放射能廃棄物貯蔵管理センターが次々と完成し操業を開始した。鳴り物入りで登場した「プルサーマル計画」の一翼を担う使用済み核燃料再処理工場とMOX燃料工場の建設も進められた。
確かに村は豊かになった。税収は4倍近くまで増え、交付金で道路や村の施設が整備された。農業や漁業、人材育成等への助成金も潤沢に用意されている。原燃や関連企業に働き口も出来た。
バス停で温泉行きのバスを待つ女性グループに話を聞いた。
「毎日温泉へ行ってお喋りして、今は天国のような生活よ」
と笑顔が返ってきた。
実際、原発事故の直後だというのに、拍子抜けする程地元の人の「核燃料サイクル施設」に対する信頼は揺らいでいなかった。
「正直、不安がないかと言えば嘘になるけど反対するつもりはない。核の肥溜め村と言われながら、日本中の原発のゴミを引き受けているんだ。どこかが引き受けなきゃならんだろう」
とFさん(57)は声を強めた。
地元反対運動を続けている女性は核燃料に頼らない村つくりを訴えている。
「再処理工場が稼働するととんでもない量の放射性物質が空気中にも海中にも放出されるんです。これ以上危険な事はやめて欲しい。自然に根ざした産業で村を活性化しなくては若い人の村離れは止められません。現状では村には原子力関連の仕事しかないのだから」
女性の話には説得力があったが、住民の多くはむしろこのまま原子力事業がストップしてしまう事の方に不安を抱いていた。
あれから10年、六ヶ所村は、次世代を見据えたエネルギーシティへと進化を続けている。豊富な財源を使って、村おこし、教育、福祉と次々と政策を打ち出し、成功した村という印象は強い。だが、これから先の村の更なる発展は再処理工場の稼働の如何にかかっている。再処理工場は度重なるトラブルで操業の見込みは立っていない。
「事故は怖いと思うが、明日から路頭に迷うわけにはいかない」
とFさんは言った。
「事故を教訓により安全になるはずだ。再処理工場は必要だ」